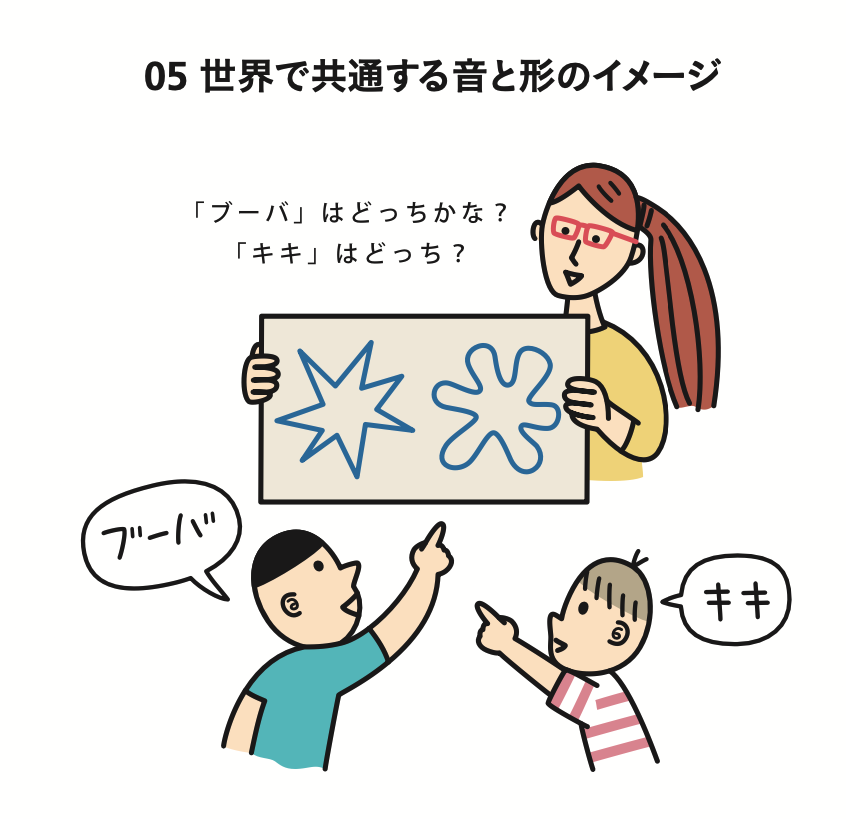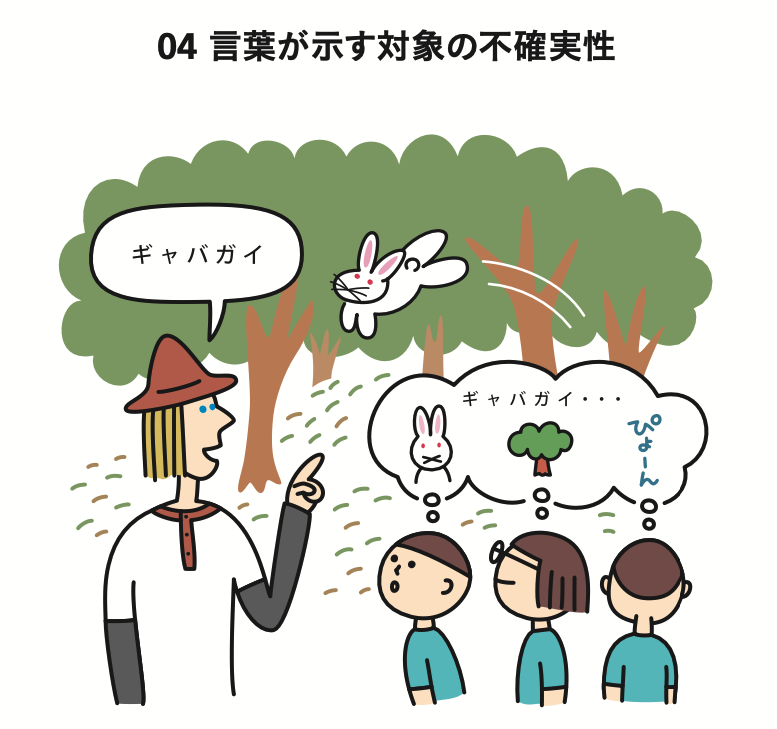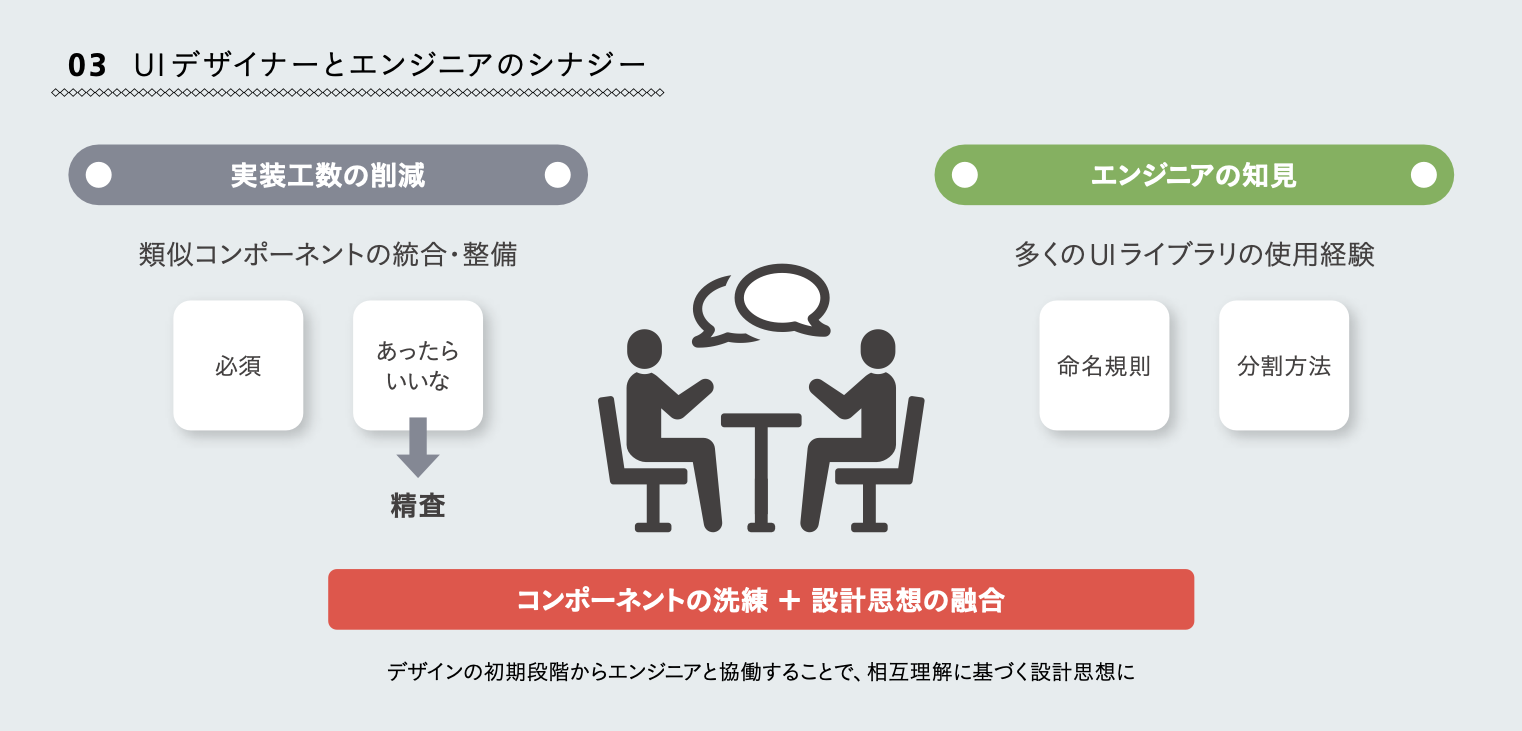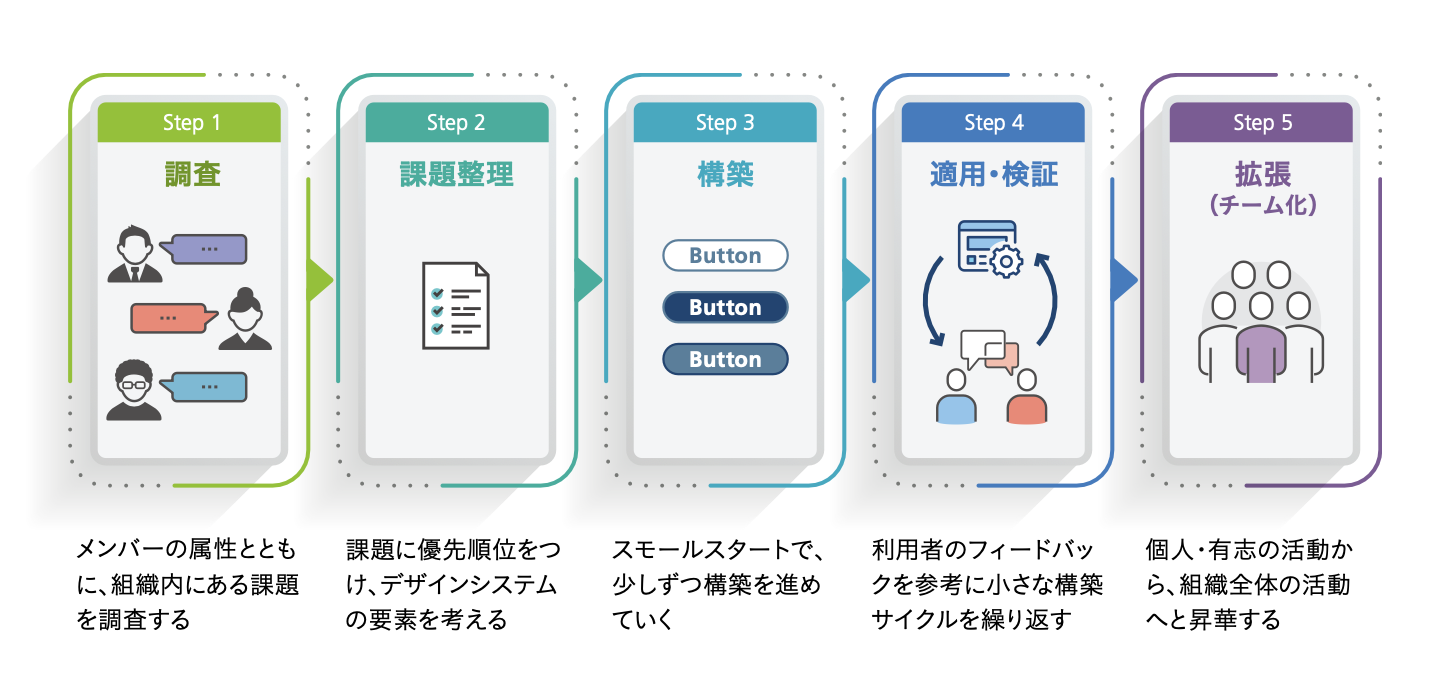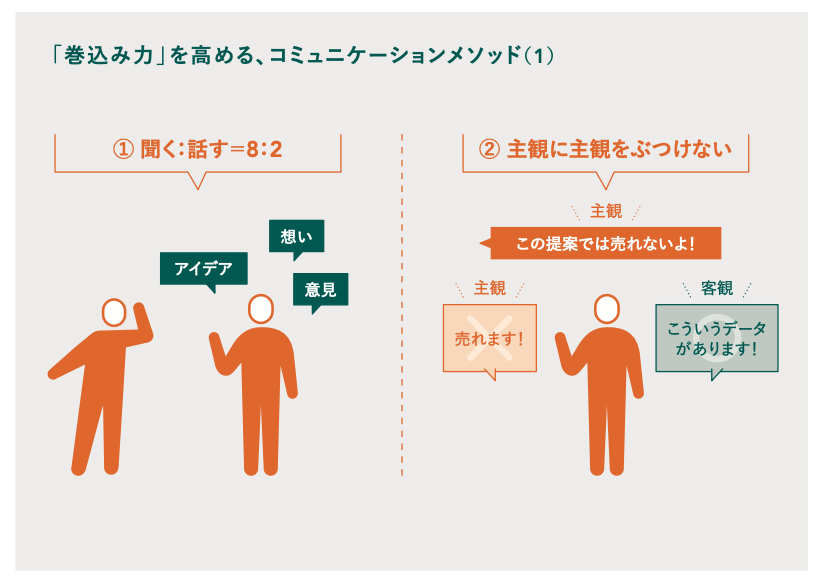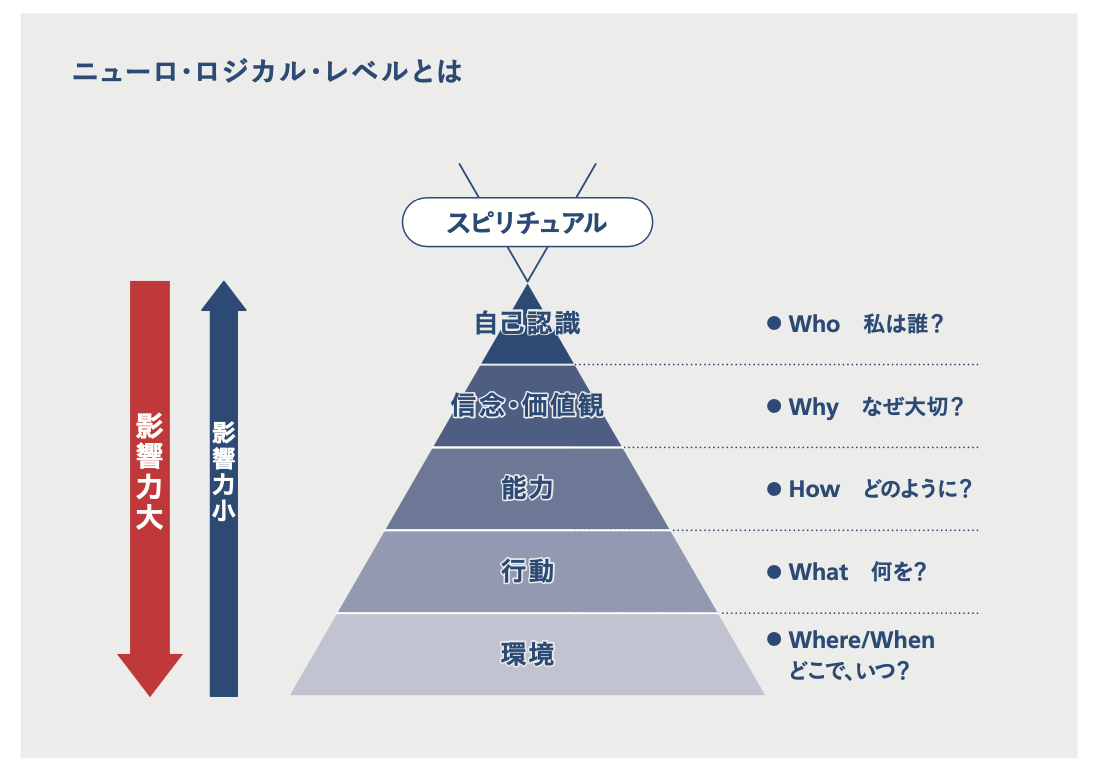Webエンジニアになろう! 第4回 Web開発の種類
Web開発をする場合、クライアントに依頼をされて制作をするのか、それとも会社の事業として制作しているのかなどによって、求められるスキルや適性が変わることがあります。
ここでは、Web開発の種類について紹介しましょう。
受託開発と自社開発
受託開発
「エンジニア(Engineer)」は英語で「技術者」といった意味で、本書で扱うWebエンジニアはもちろんのこと、機械設計をしたり、電子パーツを組み立てたりするのも広く「エンジニア」の仕事です。
開発にかかる工数やコストから「開発費用」を見積もって依頼者に提示し、納品が終わったらその金額を請求してその仕事を終わらせます。その後は、また別の依頼者からの仕事や、同じ依頼者であっても別の仕事を引き受けて、制作していくといった仕事のスタイルが主になります。
契約形態によっては、運用や開発の継続などを行って、ずっと同じ依頼者の元で制作・開発を続ける場合などもあります。
会社の場合はもちろん、フリーランスなどは受託開発が、確実に収入が得られて仕事しやすいスタイルでしょう。
自社開発・個人開発
自社開発・個人開発は、受託開発と違って依頼者は存在せず、社内のプロデューサー、プランナー(または自分自身)といった企画を考える人達が考えた企画を元に、制作を行うというスタイルです。制作したものは自社で運用を行い、利用者を増やしながら利用料や広告料などで売上を立てていきます。
基本的には、ずっと自社のサービスを維持・運用していくスタイルで、そこで働くクリエイター達も、同じものを作り続けていく形になります。
受託開発・自社開発のメリット・デメリット
受託開発と自社開発には、どちらにもメリットやデメリットがあります。
受託開発
受託開発の場合、さまざまなクライアントの依頼を引き受けるため、常に新鮮な気持ちで仕事に取り組むことができます。
新しい技術も採用しやすく、チャレンジもしやすいのが特徴です。また、企業としては開発が終われば、まとまった売上を得ることができるため、資金繰りがしやすく、少人数でも仕事量を調整して経営しやすいため、小規模なWeb制作会社が多い特徴があります。
ただし、景気などに左右されやすく、仕事量が一定にならないため、非常に忙しくなってしまう時期と、まったく仕事がない時期などと波があったり、売上のめどが立てにくいなどのデメリットもあります。
自社開発
自社開発の場合、一度ビジネスが軌道に乗り始めると安定した売上を得やすく、また仕事の忙しさも調整がしやすいため、安定して仕事に取り組むことができます。
新しい技術などを常に追い続ける必要もなく、ある程度計画性を持って仕事に打ち込むことができます。ただし、企業としては最初の開発時に多額の資金が必要となる上に、完成するまでは売上が得にくく、また開発が終わった後も、利益が生まれるまでの間の広告宣伝費や営業費用などが必要となるなど、資金繰りに苦労することがあります。
どちらのスタイルが良いということはないため、自身が求めていることや、自身の仕事のスタイルに合わせて、選ぶと良いでしょう。
派遣会社・SES
制作会社やネット事業会社で、大規模なプロジェクトなどが開始されたときに、一時的にWebエンジニアが不足した場合、戦力として相手先の会社に常駐するなどして開発に参加するというスタイルです。
派遣やSESなどの相手先に常駐して行う仕事は、受託開発以上に仕事自体の数は多くあります。派遣とSESの違いは、依頼主との契約形態の違いにあります。
業務委託
フリーランスエンジニアがクライアントの企業と仕事をするときに結ぶことが多い契約形態です。あるプロジェクトの開発を依頼されて、その開発に携わります。業務委託は、契約の形態によってさらに次のように細かく分かれます。
請負契約
業務の「成果物」の納品を約束し、それに対して報酬が支払われる契約形態です。例えば、Webサイトの制作を「請負契約」で請け負った場合、Webサイトを完成させて「納品物」として納めるという契約形態です。
委任契約・準委任契約
成果物の納品は行わず、業務を行う時間などによって報酬が発生する契約形態です。運用されているWebサイトの保守業務や、監視業務、コンサルティング契約などがこれに当たります。 SESが行う契約形態もこちらになります。
なお、委任契約というのは一般的に弁護士や税理士などの「法律行為」を行う業務を指すため、Web制作では「準委任契約」である場合が多いです。
派遣契約
派遣契約の場合、業務委託とは違って「仕事」を引き受けるというよりは「労働者の派遣」を行い、派遣先の企業がその労働者に指揮命令をすることができるという契約形態です。
派遣契約を行うには、派遣元の企業に「労働者派遣事業許可」という厚生労働省による許可が必要で、これには多くの条件を満たしていなければなりません。
安易には判断せず、少しずつ「お金」や「税金」に対する知識を身につけながら、自分に合ったやり方を見つけていくと良いでしょう。
※本記事は『Webエンジニアを育てる学校』の本文を一部引用・再編集しています。
『Webエンジニアを育てる学校』発売1周年記念キャンペーン中!
『Webエンジニアを育てる学校』は現在お得なキャンペーンを行っています! 詳細はこちら