【コラム】コンテンツ疲れから考える“コンテンツ戦略”
新常態下で、オンラインコンテンツと向き合う時間が増えてきました。SNSなどでは毎日大量のコンテンツが流れてきますが、私はというと少しコンテンツ疲れのような状態に陥っています。その量もさることながら、それぞれのコンテンツの在り方について疑問を持つことも少なくありません。今回はその疲れの原因を紐解き、今後のコンテンツ戦略のヒントを探したいと思います。コンテンツと言っても幅広いので、主にWebの記事や動画について絞って考えていきます。
まず、私がコンテンツ疲れを実際どういうときに感じるかなと考えたときに、真っ先に思い浮かんだのが「タイトルのミスリード」です。SNSなどでちょっと気になるタイトルのリンクを見かけて、飛んで読んでみたら全然思ってたのと違う、という体験は誰にでもあると思います。これは本当に疲れます。
ミスリードにも種類があり、タイトルで約束した情報がなかった場合と、タイトルの醸し出す雰囲気やノリが中身と違う場合があります。新しさを彷彿とさせるタイトルでも内容がそうでなかったり、いい加減な内容かと思えば意外と真面目で濃いものだったり、タイトルから期待されるものと違ったものが出てくると、その振れ幅に疲れてしまいます。
私も編集長として記事編集時によく「タイトルの期待値コントロール」ができてない、と感じることがあるのですが、コンテンツの性質に即したタイトル付けは非常に大切だと思っています。タイトルがコンテンツの内容を表すのはもちろん、どういうテンションで見てほしいかを表すのもまたタイトルです。
コンテンツを見終わった後にタイトルを見て、「あれ、こんなこと言ってなくない?」「思っていたノリと違ったな」と思うくらいならまだいいのですが、最初から期待した内容や雰囲気があって、そうじゃないと思った瞬間にユーザーは時間を無駄にした、と強く感じてしまいますし、どんな良質なコンテンツでも、即離脱してしまいます。誰もがコンテンツの文脈に沿ったタイトル付けにこだわっていければ、コンテンツの海も少し泳ぎやすくなるのではないでしょうか。
コンテンツ疲れの要因をもう一つ挙げると「テンポの悪いコンテンツ」が多いことです。これは動画に多いかもしれませんが、関係のない前置きが長かったり、自分語りが多めだったりと、早く本題に入ってほしい! と思うことがあります。
繰り返しになりますが、私たちのまわりにはコンテンツが溢れかえっており、人は貴重な時間を使ってコンテンツを楽しんでいます。ですが、発信側の多くは自分たちのペースで丁寧な背景を説明し、自分たちの世界を構築しようとするわけです。例えるなら、カラオケでメンバー全員が終始ミスチルの壮大なバラード曲を歌い続けているかのようです(もちろんそういうコンセプトの集まりならいいのですが笑)。
詰まるところ、自分たちのコンテンツが数多あるコンテンツの中の一つであるという意識が大事なのだと思います。この辺りは人気YouTuberの配信がすごく勉強になります。彼らの台本は単刀直入で、時間もコンパクトにまとめているため論点もはっきりしており、コンテンツ過多な世の中のデファクトスタンダードになりつつあります。
総じて、コンテンツ過多な時代において、コンテンツのつくり方も変わっていくということなのかもしれません。より直感的にわかりやすいコンテンツの設計をすることで、ユーザーは情報の海の中でも欲しい情報にストレスなくたどり着けるようになるのではないでしょうか。
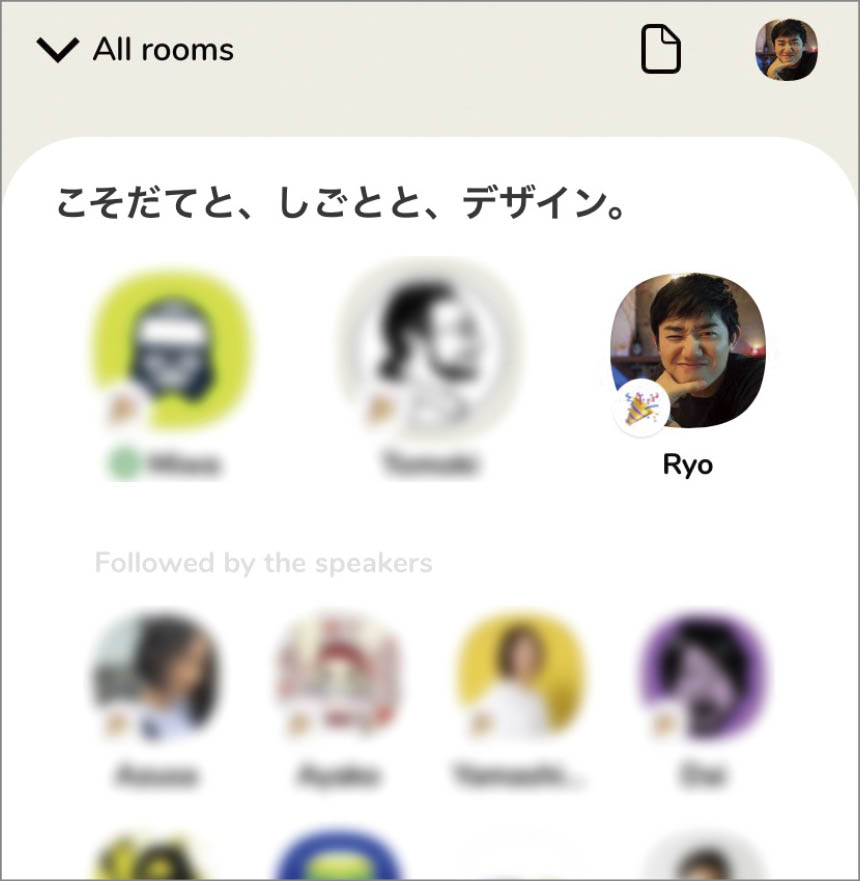

- ナビゲーター:三瓶亮
- 株式会社フライング・ペンギンズにて新規事業開発とブランド/コンテンツ戦略を担当。
- また、北欧のデザインカンファレンス「Design Matters Tokyo」も主宰。前職の株式会社メンバーズでは
- 「UX MILK」を立ち上げ、国内最大のUXデザインコミュニティへと育てる。ゲームとパンクロックが好き。
個人サイト: https://brainmosh.com Twitter @3mp
