【IoT×農業】「e-kakashi」が変える農業の姿●特集「IoTの現在」
農業に必要な経験や勘をIoTでデータ化する
IoTが活躍できる産業の一つとして特に注目されているのが農業分野。農林水産省発表の「平成26年 新規就農者調査」(2015年9月発表)によると、49歳以下の新規就農者は2万1,860人。新規就農者全体の約38%を占めるなど、農業を始める若い世代が増えている。しかしその一方、定着する人が少ないという問題を抱えている。理由はさまざまだが、大きな要因の一つとしてあげられるのが、農業は経験や勘に頼る点が多いこと。つまり意欲を持って農業を始めてみても栽培がうまくいかず、最終的に離職してしまうケースだ。そうした新規就農者をサポートするために、JAや各自治体には「営農指導員」や「指導農業士」と呼ばれる人がいるが、高齢化や人手不足などで、支援できる範囲や人数も限りがある。
そんな農業が抱える課題をIoTで解決する取り組みとして注目を集めているのが、ソフトバンクグループのPSソリューションズ(株)が開発した「e-kakashi」だ。
e-kakashiは、温湿度センサーや日射センサー、土壌水分センサーなど、栽培と密接に関わる各種センサーを搭載した子機を田んぼや畑に設置して栽培現場をモニタリング。収集したデータを、子機から最大1km圏内に設置した親機の携帯回線を経由してクラウドに送ることで、農業に活かすシステムだ。2015年10月にソリューションの販売を開始し、同年12月末にサービスインした。
e-kakashiの開発を担当した同社の坂井洋平氏は開発の経緯をこう説明する。
「e-kakashiは、ソフトバンクグループの携帯電話ネットワークを使った新規事業の一つとして、2008年にスタートしました。今はさまざまな産業にITが参入していますが、農業分野にはほとんど参入できていないのが現実です。そこで農業が抱える課題をITで解決できないかと考え、スタートしたのがe-kakashiでした」
わずか数人のグループで発足したこのプロジェクト。当時はまだIoTという言葉は使われていなかったが、データを収集してクラウドにアップするというコンセプトは当時から変わっていないという。だが、当初、考えていたのは取得したデータを可視化するところまでで、取得したデータの具体的な活用方法や、農業の抱える課題へのソリューションを提案するところまでは想定していなかった。だが、調査を進めるうちに、データの可視化だけでは役に立たないことがわかってきた。
「私たちは遠隔で栽培環境の観測ができれば、農業に携わる方にとって何かしらの価値が生まれるのではと考えていました。でも、たくさんの人の意見を聞くうちに、気温や湿度の変化や推移を知るだけでは、まったく役に立たないことがわかってきたんです」(坂井氏)
データと人の経験を融合してソリューションに
そこで農業に精通した人材をチームに招き入れ、どういうデータを収集し、どう活用すれば農業のソリューションとして提供できるのかを検討。e-kakashiが集めたデータを栽培に必要な知識や知見と組み合わせて、「ekレシピ」として提供することにした。ekレシピとは、これまで人の経験や勘、ノウハウに頼っていた部分やe-kakashiが収集したデータをもとに、地域や農作物ごとの栽培方法としてまとめた情報のこと。いわば栽培方法のレシピだ。
「e-kakashiはIoTでデータを取得するハードの部分と、人の知識を蓄積、共有するekレシピの二つの要素で成り立っているのが大きなポイントです」
こう説明するのは同社リードソリューションアーキテクトの小杉康高氏。
たとえばe-kakashiをすでに導入している京都の与謝野町では、米を育てるのに理想的な栽培環境を地域の指導員が入力し、ekレシピとして公開。e-kakashiを導入している農家がこのレシピを取り込むことで、自分の田畑で収集したデータの変化によって、病気に注意するタイミングや、収穫の時期など、栽培に関するさまざまなアドバイスや注意がWebアプリを通じて通知される仕組みだ。

作物や地域ごとに、栽培に必要なノウハウや知見が入力されているデータ。e-kakashiの利用者は作成者の承認があれば、レシピを取り込むことができる。現在、ekレシピは自社の専門チームの他、主にJAや各自治体の指導員が作成しており、作成者は情報公開の範囲も設定できるようになっている。たとえば必要な作業が発生した時はアラート通知のみで、理由は出さないなど、今後、広がっていくであろう展開を見据えた仕様になっている。
これによって、指導員が各農家に伝えていた経験やノウハウ、知見が、データに基づいて誰もが扱うことができる情報へと変化する。企業でも農業でも、新入社員が独り立ちするまでは多くの時間と労力がかかるが、指導員がこれまで培ってきた経験や勘を「eKレシピ」という形で数値化や形式化されることで、栽培方法を多くの農家と共有できるようになるわけだ。
「今まで農業を指導してきた方は、指導内容が共有・連携できる価値を持つとは考えてもおりませんでした。しかし、家庭内だけで共有されていた料理方法がレシピサイトによって多くの人にとって価値ある情報に変化し、共有されています。ekレシピも同じ考えです。さまざまな農作物がその土地に最適な方法で栽培されていますが、その方法は、指導員や実際に栽培している農家の方しか把握していません。その知見をデータ化して共有すれば、新しく農業を始める方もスムーズに栽培できるようになるはずと考えたんです」(坂井氏)
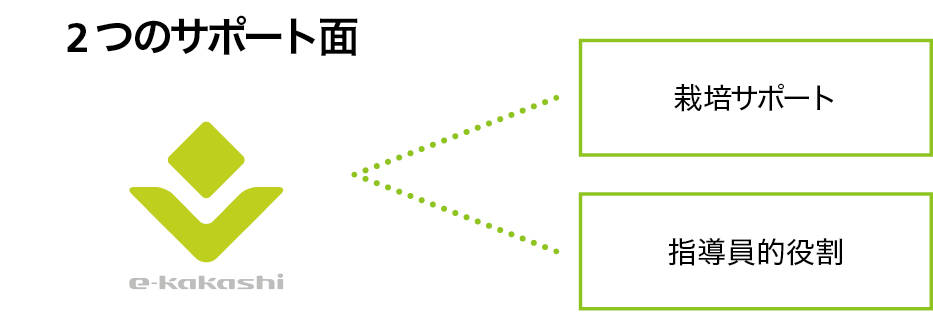
Googleが集めないデータを収集する
サービスインして間もない今は、各農家ではなく、農家を指導する立場にあるJAや各自治体等に普及を進めている。これにはekレシピの数を増やしたいという意図があり、2016年中には500拠点の普及を目標にしているという。
「e-kakashiが普及して、地域ごと、作物ごとにekレシピが増え、たくさんの人がekレシピをつくりたいというムーブメントを起こしたいと考えています。もちろん、海外への展開も視野に入れています」(坂井氏)
だが、まだまだ事業はスタートしたばかりで改善点も多いという。なかでも、特に力を入れていきたいと小杉氏が話すのはセンサーの充実だ。現在、e-kakashiの子機には4つのセンサーが搭載されているが、一つでも多くのデータが収集できれば、それだけ“レシピ”の精度が高まることになるからだ。
「土壌のph値など、収集できれば農業に役立つデータが他にもたくさんあります。e-kakashiは拡張のためのポートも備えているので、これからもセンサーの充実も進めていきたいと思っています」(小杉氏)
さらにIoTによって収集したビッグデータを別の形で活用したり、今は取得できていないセンサーの開発にメーカーが新規参入したり、ekレシピがさまざまな人から投稿されたりと、e-kakashiが新たな農業プラットフォームになる可能性も秘めている。
「Googleが集めていないデータを収集する」という思いから始まり、農業の課題解決に挑むe-kakashi。そのコンセプトは、「カンタン」「手軽」「面白い」で、農業に携わる人や団体からは、「いらないと言われたことはない」というほど、業界の反響は大きい。
IoTにより、データと人の経験や知見が融合することで、農業に大きな革命が起きる日はそう遠くないかもしれない。

写真左:農業IoT事業推進部 農業IoT事業推進課 課長 坂井洋平氏。写真右:農業IoT事業推進部 農業IoT事業推進課 リードソリューションアーキテクト 小杉康高氏
