【コラム】SNS時代に育む「もっともっと好き」
こんにちは! 大阪のちょっとやんちゃな八尾という地域にある社員35名の老舗石鹸屋で商品企画・広報を担当している峰松です。
普段、新商品の開発やプロモーションをローンチした後に一番気になるのは、消費者が実際にブランドのことをどれだけ好きになってくれたか、です。「エンゲージメント」という言葉も元をたどれば意味するところは同じですが、今ではどちらかというと、SNSの効果測定のための具体的な数値という文脈で使用されているように感じています。
ご縁があって、昨年4月から近畿大学の文能ゼミと共同プロジェクトを行いました。ゼミは主に中小企業の研究を進めており、実際の企業課題について考えるケーススタディを授業にしたいということで、私に白羽の矢が立ちました。そこでこの一年、「どうしたらブランドをもっと好きになってもらえるか?」を考え、体験してもらうことにしました。わたし自身も毎日のように試行錯誤しているテーマです。学生さんにとっては荷が重いかなと思ったので、現場でつくっている人や、企業の隠されたストーリーを探るという方法に絞り込みました。
実際に大阪の中小企業各社を訪問し、チームごとにインタビュー記事を起こしてもらったのですが、何気なく日常で使っている商品の知らないエピソードがたくさん聞けて、とても興味深い内容ばかりだったのです。
わたしも、事前に経営者やメーカーのインタビュー記事を探していたところ、偶然見つけたのが、全国で「靴下屋」を展開するタビオ(株)の会長インタビューです。それからというもの、すっかりタビオのファンになってしまいました。
24時間、靴下のことだけしか考えず、どんな言葉も靴下と聞こえてしまう。靴下の良し悪しを判断する感覚が鈍らないよう、普段は裸足で生活。百貨店で高級靴下の品質を確かめたくて、こっそり噛んで確認したエピソードなど…「靴下バカ」を通り越して、もはや「靴下界の神様」です(笑)。以降、靴下を買うときは必ずお店を覗くようになりました。
SNSの登場で、低コストかつ身近に消費者とコミュニケーションが図れるようになり、わたしたちのような資本力のない中小メーカーでも、消費者の「好き」を醸成する活動がしやすくなりました。だからこそ、今まで以上にどんな会社の、どんな人が、どんな哲学でつくったものなのかが伝わらないと、選ばれないよなぁと、そんなことを考えている今日この頃です。

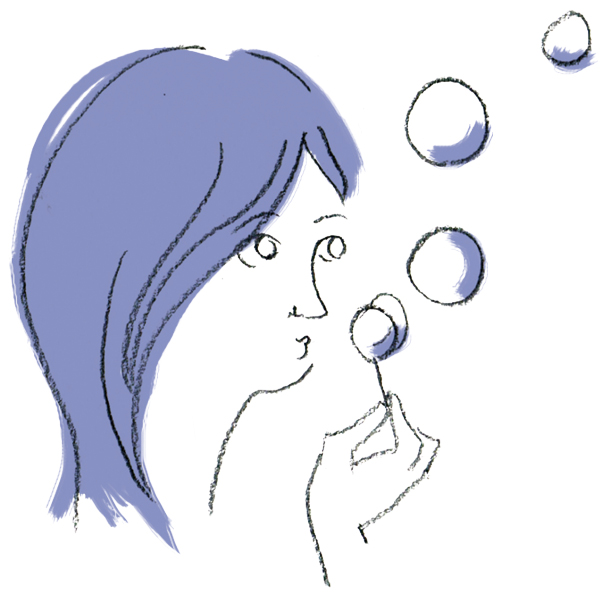
- ナビゲーター:峰松加奈
- 新卒で外資系消費財メーカーに入社し、2015年夏より大阪の中小企業・木村石鹸工業(株)に転職。商品企画部門がなかったため、マーケティング室を立ち上げて自社ブランドの開発・育成に日々奮闘中。目標は、今までにない革新的なブランドを作って、「家事」の概念を変えること。木村石鹸ブログ:http://www.kimurasoap.co.jp/blog/ Twitter:@mnmtkn
