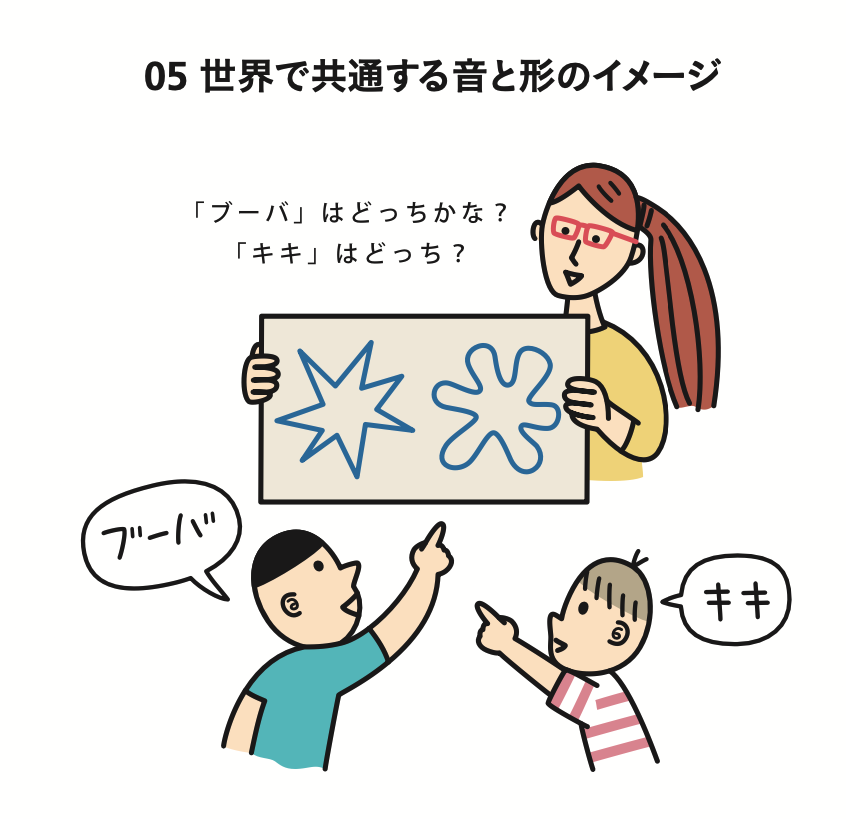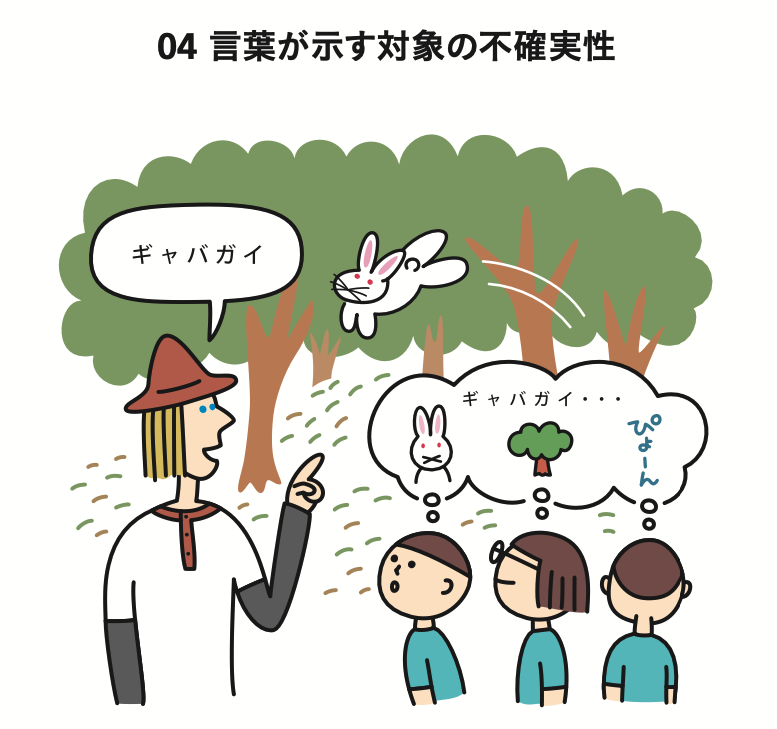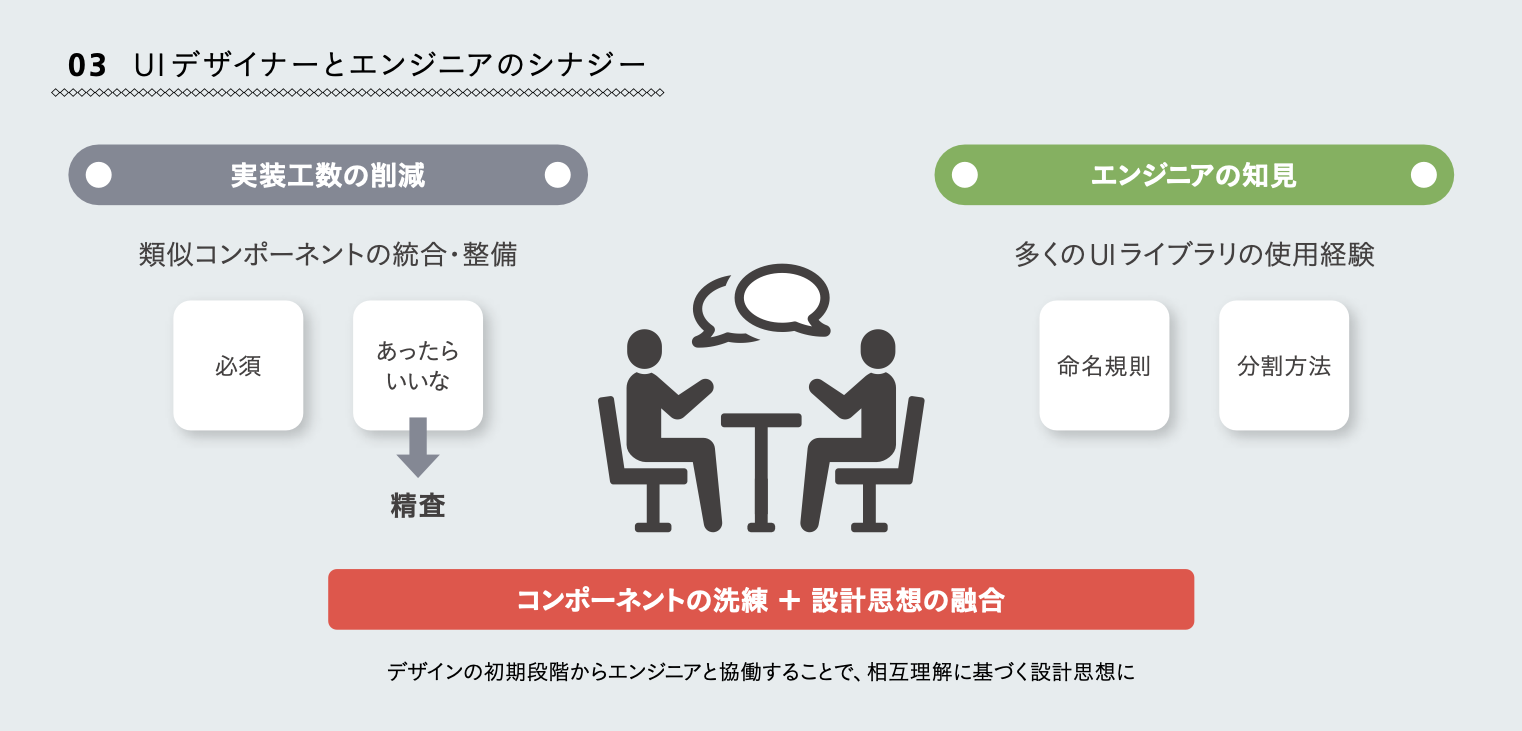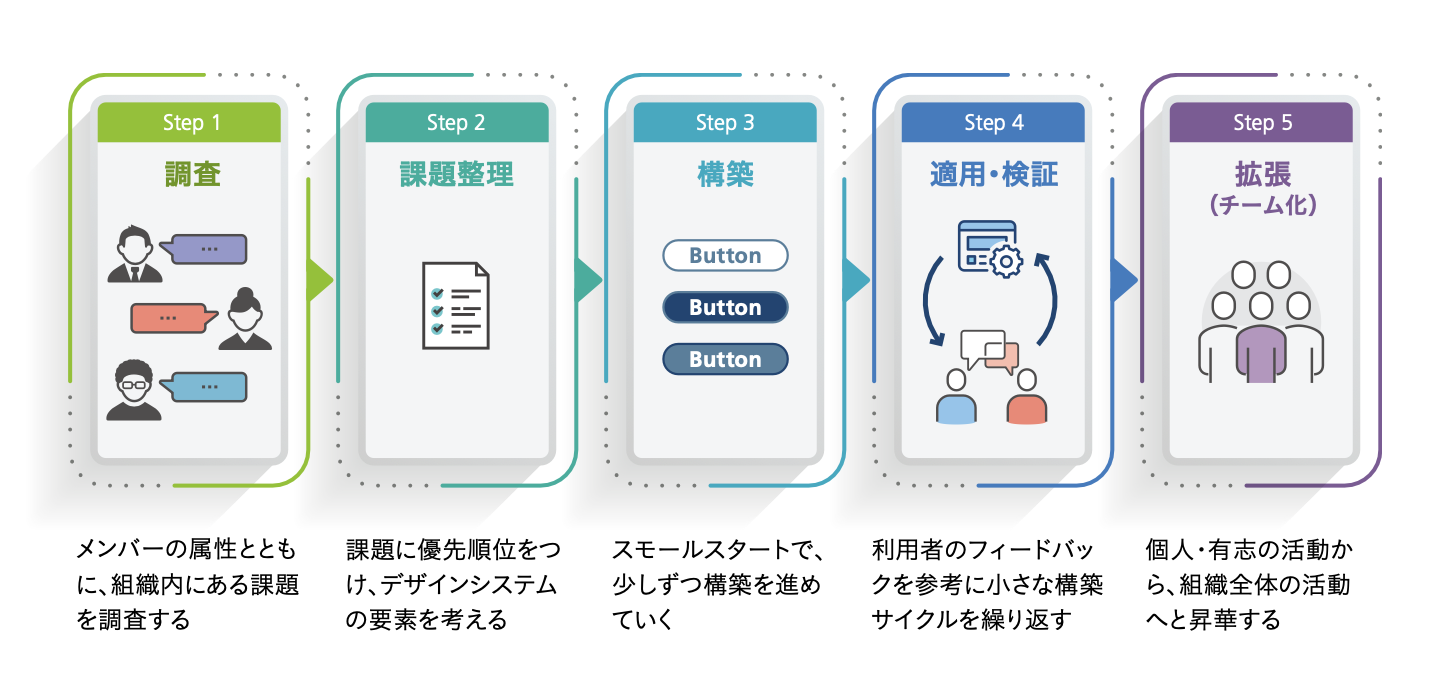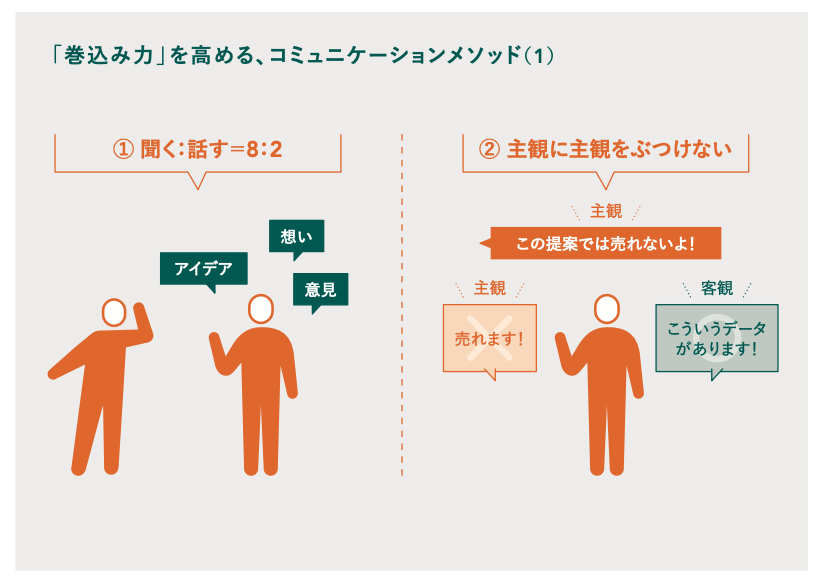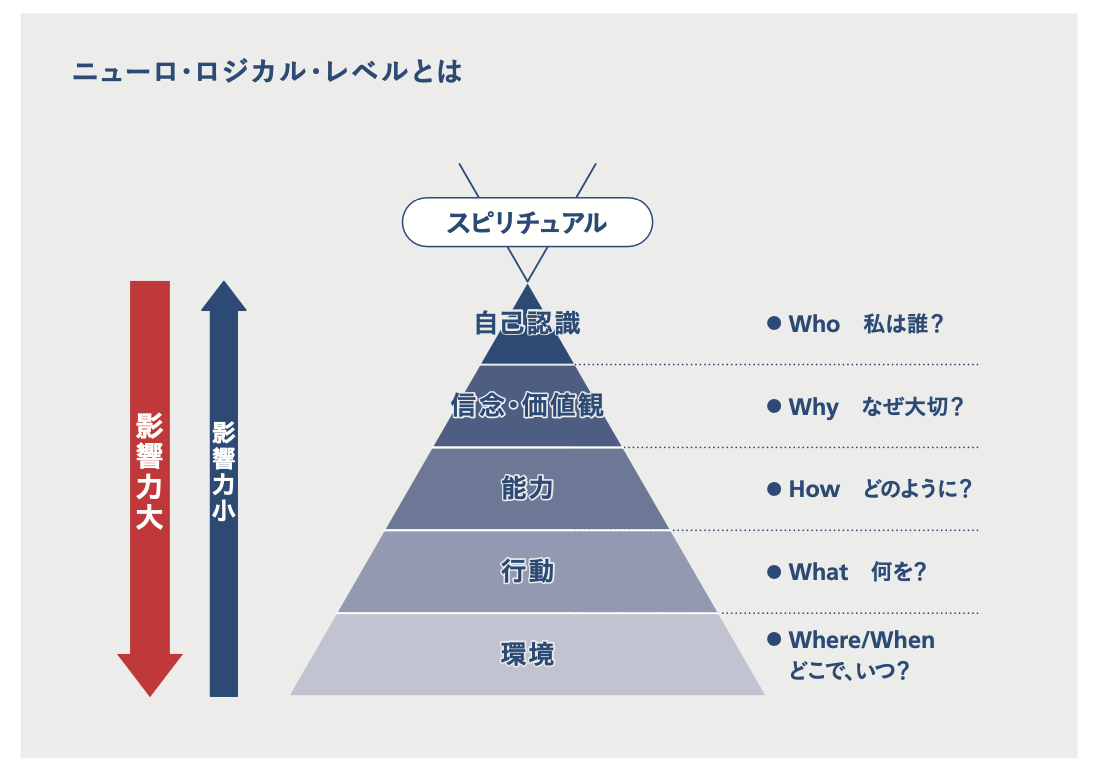最新の“ 就活”データから新卒&中途採用のニーズを読み解く
空前の「売り手市場」というのは本当か?
この3、4年の就活市場を表すものとして「超売り手市場」という言葉が用いられることがある。総務省の調査によると2018年4月の完全失業率は2.5%と低水準で推移しており、厚生労働省による同月の有効求人倍率は1.59倍と正社員については過去最高の水準を記録している(いずれも季節調整値)。確かにこの数値だけ見れば、景気回復を背景として企業側の採用活動が活発化し、新卒・中途採用問わず求職者側に有利な状況になっていると考えるのが自然だろう。
ところが、実際に就活を行っている新卒学生の声を聞けば「書類審査の時点で落とされる」「30社受けても内定が取れない」など厳しい現状も窺える。こうした採用における需給ミスマッチの要因の1つとして挙げられるのは、根強い「大企業・有名企業志向」の強さだ。
確かに大企業には事業のスケール感や福利厚生制度の充実など魅力的な点は多い。しかし、それゆえに応募倍率が中小企業と比べ極端に高くなっている。リクルートワークス研究所が発表した2019年卒の「大卒求人倍率調査(大学院卒含む)」によると、従業員規模が300人未満の民間企業では求人倍率が過去最高の9.91倍、一方、300~999人では1.43倍、1000人~4999人では1.04倍、5000人以上では0.37倍となっている。
つまり、「超売り手市場」なのはあくまで中小企業の話で、いわゆる大企業では1件の求人を2~3人で競い合っていることが裏付けられている。就職情報サイトがオンラインで実施する「学生就職モニター調査」においても、半数以上の新卒学生が、大企業志向であることがわかる(図1)。
最近の新卒学生が「給料」よりも重視すること
では、このような状況下で、学生はどのような基準で企業を選択しているのだろうか。2019年卒については前述の学生就職モニター調査に詳しく記載されていた。ここで注目したいのは「企業を選ぶときに、あなたが特に注目するポイント」という項目だ。
データには月次の変化や性別、専攻といった属性別にランキングで集計されているが、本記事では全体的な傾向をつかむために合計の数字を元に注目すべき要点のみをご紹介しよう。
このランキングでは「自分が成長できる環境がある」や「社員の人間関係が良い」といった項目をもっとも重要視するポイントとして挙げる傾向があり、時期や性別、専攻などでランキングの順位が大きく変動することはない。
そして、もっとも注目する項目を1つだけ選ぶ場合でも、最大3つの複数項目から選んで回答する場合でも同様の傾向が見られ、最近の新卒学生が企業に対して自分がそこで社会人として通用する人材へ成長できることを期待しているのがわかる。
また、「福利厚生や制度の充実度」「給与や賞与が高い」「希望する勤務地で働ける」といった働き方についても関心が高いことが示されているが、これは働き方が注目されている昨今では当然の要望だろう。それよりも、自分のポテンシャルを引き出せることを重視している点が注目に値する。
なお、その一方で上の図には含まれていないランキング下位の項目としては「商品企画力がある」「職業別採用がある」「平均勤続年数が長い」といった項目がある。また、「女性が活躍している」のように男女で注目度が10倍以上分かれる項目もあるなど示唆に富んだデータであったのでチェックしてほしい(https://saponet.mynavi.jp/release/)。
職場を体験するインターンシップが重要な理由
最近の新卒学生が「自分が成長できる環境がある」や「社員の人間関係が良い」といったポイントを企業選びの際に重視していることがわかった。これらはいずれも公開された企業情報だけでは読み取れないものだ。実際に働くことを希望している企業に赴き、現場の空気に触れ、将来一緒に働くであろう従業員の働きぶりを見たり生の声を聞くことではじめて得られるものとなる。
前述の学生就職モニター調査には内々定保有者の活動状況を集計したデータもあり、ここではモニター学生が利用した企業の発見ツールの利用状況について、主だったものを確認できる。1人当たり最大4社回答した結果を内々定先1,411社で集計したところ、上位から「インターンシップ」(25.4%)、「就職情報サイト」(22.7%)、大規模な就職イベントなどの「合同企業説明会」(15.2%)、「学内の合同企業説明会」(6.6%)、「OB・OG先輩社員」(6.0%)、「企業ホームページ」(5.7%)と続いている。他にも「新卒紹介サービスからの紹介」や「親、親類、友人」からといった中途採用では比較的よく見られる手法は、新卒に関しては少数派にとどまった(図3)。
ここでのポイントは、学生にとってインターンシップが志望する企業を発見するのに重要な役割を担っていることだ。同調査の別の設問でも、その企業に入社したいと最初に強く思ったタイミングは「インターンシップ参加時」がもっとも高く、実に29.8%にも上っていた。
就職活動をマーケティングにおける購買意思決定プロセスになぞらえれば、認知するだけでなく「行動(Action)」や「体験(Experience)を引き起こすタイミングが重要だ。インターンシップは新卒学生にとって企業の中身や職場環境を知るための重要なツールとして機能していることがわかるだろう。
それにもし最終的にその企業への就職を希望しない、不採用となったとしても、すでにその企業にとってインターンシップ参加者は潜在的な顧客・推奨者となっているのだから、体験の満足度を高めるための施策を検討する必要があるだろう。
採用側とのミスマッチの溝は埋めていけるか
最近の新卒学生が企業選択の際に重視するポイントと、それを探す手段や決めるタイミングについて理解したところで、採用する側の企業の姿勢についても改めて確認しておこう。
1,024社の企業(上場79社・非上場945社/製造407社・非製造617社)の新卒・中途採用の人事担当者が人材雇用に関して回答する「企業人材ニーズ調査」では、広範なリサーチ結果について知ることができる。
その中で「採用の理由やスタンス、採用手法について」の章から重要な部分と思われるものをピックアップしてみた。元資料では雇用形態別に正社員(新卒・中途採用)、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトごとの調査結果や企業規模や業種、本社所在地エリア、従業員ごとの分布が記されている。ここでは、結果をわかりやすくするため、正社員(新卒・中途採用)に限定し、「採用の理由」(複数選択)の上位7項目のみ絞り込んで掲載している(図5)。
すると、全体的には新卒は「企業の年齢構成を若返らせるため」、中途採用は「人手不足を補うため」という大きな目的が窺える。当然ながら個別の事情は企業によってさまざまで、多くは正当な理由であろうが、この採用側と求職側の意識の温度差がミスマッチを生んでいるように思えてならない。
また、同調査には「人材のミスマッチ」と感じられた具体的な理由についても調査がなされている。結論だけかいつまんで言えば、本人の能力そのものよりも「人間関係がうまく行かない(馴染めない)」「すぐに辞めた」が上位回答となっている。こうしたミスマッチを完全に解消することはできないにしても、採用の段階でマッチングの精度を高めるための施策を行う必要性が企業(特に中小企業)にとってますます高まっているのは間違いないだろう。