トップランナーたちに生で聞いた! ビジネス価値を発揮するWebサイト最前線。「web professional summit by Orizm」密着レポート

ちょっと株式会社は、2025年4月23〜25日に開催された「営業・デジタルマーケティング Week」に出展し、同社が開発・提供する次世代Webサイト構築プラットフォーム「Orizm」のPRを行いました。ここでは、同社が登壇した事務局主催のオープンセミナーと、出展ブースにて開催したトークセッション「web professional summit by Orizm」から一部の模様をレポートします。
オープンセミナー「生成AI×Web制作の最前線 リアルな活用法と現状の課題」
会期2日目の4月24日(木)、展示会事務局主催のオープンセミナーに、ちょっと株式会社の小島芳樹さんが登壇。株式会社キテレツのカイトさん、スタジオスプーン株式会社の中村明史さんと共に「生成AI時代のWebサイト最新事情」について語りました。

Web制作現場の最前線におけるAI活用
小島芳樹(以下、小島) 本日は、キテレツのカイトさん、スタジオスプーンの中村さんをお迎えし、「AIとWeb制作の現場での関わり」についてお話を伺っていきます。
近年、Web制作の現場でも、コンテンツ生成やコードの自動化、接客支援など、AIの導入が急速に進んでいます。カイトさんの制作現場では、AIを活用する場面はあるのでしょうか?

カイト はい。もっともよく使っているのはテキスト生成で、社内にコピーライターが1人いるような感覚で、日常的にAIを活用しています。コードも一部、AIに生成させています。
テキストライティングでは「Claude」が特に優秀だと感じています。コード生成には「Cursor」というAIエディターを使っていて、最近では「Devin」や「Cline」なども試しています。
少し変わった使い方では、オンライン講座の教材用に架空のクライアントを設定する際にもClaudeを活用しました。「宇宙人の言語を学べる語学学習サイト」という設定で、異星の言語や講師キャラクターをAIが考案し、それをベースにWebサイト制作を学ぶという内容です。

小島 面白いですね。スタジオスプーンさんはグラフィカルなWebサイト制作に強い印象がありますが、生成AIは活用されていますか?
中村明史(以下、中村) 現在は補助的な活用が中心です。特にアニメーションやグラフィック表現の分野では、単純な処理であれば活用も考えられますが、複雑な表現になるとまだまだ難しさを感じます。
AIは、算術のような普遍的な処理には非常に速く正確な答えを返してくれますが、私たちが日々向き合っている思考と試行錯誤の繰り返しによる表現領域は正解がない分、多様なアプローチが存在します。
例えばAfter Effectsでイメージをつくり、それをTypeScriptやシェーダー言語で実装する方法の場合、人間同士でも言語化や業務連携が難しいことも多く、そうしたものはやはり、AIにも的確に汲み取ってもらうのは難しく感じます。

小島 AIの導入によって、作業の効率化や時間の短縮といった効果はよく聞きますが、それ以外に感じている変化はありますか?
中村 これまで手を出しにくかったプログラミング言語に触れるハードルが、大きく下がりました。書籍・教材・セミナー・テックブログといった「独学のための座学情報」と異なり、AIの場合はまるでマンツーマンレッスンのように質問をしながら、自身の見識や把握状況と突き合わせながら理解を深めていくことがとてもしやすくなりました。
小島 これまでは、チュートリアルを一通りこなしてキャッチアップするだけでも、丸一日かかるような感覚がありましたが、そのハードルは確かにグッと下がりましたよね。カイトさんは、どう感じていますか?
カイト AIはアイデア出しが得意で、自分の発想が広がる感覚がありますね。あと、最近はMCPを使った連携にも注目しています。プロンプトから3Dソフトでモデリングしたり、ブラウザと連携してテストを自動化したりすることも可能になってきました。
AIを使う難しさと、現時点での課題
小島 その一方で、逆にAIを使う難しさや、課題を感じていることはありますか?
中村 効率化を目指して、周りの方々の活用事例や自分たちなりの活用方法を検証しましたが、まだ「実務レベルやクライアントワークに使うのは難しい」と感じています。
自分たちを靴屋さんでたとえるなら、私たちのお店はフルオーダーで一足ずつ仕立てるような仕事の仕方を選んでいます。足のサイズは? ライフスタイルは? どんなシーンで履くのか? どんな自分になりたいのか?–––––そうしたヒアリングをもとに提案を重ね、ようやく形にしていく。このプロセスでは、お客様のニーズを深く理解する必要があります。
ただ、そのニーズは非常に霧がかっていて、人間でさえ理解が難しい。組み立て・製造プロセスにおいても、きめ細やかな配慮と丁寧な仕事の積み重ねが重要となりますが、AIに任せた場合「一見それらしい成果物」は手に入るものの、その中身を見ていくとメンテナンスが山ほど必要な状態だったりします。その確認と手直しを繰り返すくらいなら、イチから作り直したほうが、やはり今はまだ望ましい状態と感じています。
実際に、社内の熟練エンジニアにシンプルなLPを1枚分、MCP(Model Context Protocol)を活用してFigmaからソースコード生成までのプロセスを実験的に1週間集中して取り組んでもらったのですが、結果は効率化できた部分よりも手を加える作業のほうが多くなり、「自分で書いたほうがQCDすべてにおいて勝る」という結論に至りました。
カイト 私も、現時点ではチームの中で“手伝ってもらう”形が適していると考えています。ただ、おそらくいつかは、完全にAIに任せられる日が来ると思っています。
でも、それに抗うつもりはありません。そうなったら、私たちはAIにできないことを見つけてやればいいだけです。その必要はきっとあると考えていて、だからこそ、AIと一緒にやっていこうという気持ちでいます。
小島 そうやって作業時間に余裕ができた分で、お客様へのヒアリングを増やすなど、有意義な活用につながっている感覚はありますね。
今後は「生成AIにとって読みやすいサイト」がテーマに?
小島 では最後に、今後どのように生成AIと付き合っていくべきだと考えていますか?
中村 よく耳にする表現ですが、現在は「世界中のあらゆる事象に対して博識な新入社員が入ってきてくれた」として捉えています。知識は豊富だけれど、お客様やエンドユーザーにおけるユニークな情報や価値観については何も知りません。
でも、今はそれを伝え理解してもらうことができます。コンテクストさえ理解してくれれば、新入社員の状態から少しずつ育っていきますし、私たちもAIから知識をいただけるようになる。そんな“架空の仲間”と一緒に働いているような感覚を持ちながら、日々、実験的に取り組んでいます。
カイト 私は、「AIが本当に何でもできるようになればいいな」と思っているんです。むしろ、私たちの仕事を奪ってくれるくらいに成熟した世界を見てみたいですね。
もちろん現状では、制作の仕事で求められるような細かなディテールまで、AIにクロージングを任せるのは難しいです。でも、調査や資料作成など、制作以外の領域ではすでにかなり役立つと思いますので、皆さんも積極的に活用していただきたいと思います。
小島 私は、生成AIによってWebの画面がもっとパーソナライズされるようになることに期待しています。同じ情報でも、見る人に合わせて最適化されたUIが、適切なアクセシビリティで表示されるようになれば、いまのように“一律の内容を全員に届ける”という環境から、大きく変わっていくのではないでしょうか。
これまで私たちは、検索エンジンに対して“いい感じ”に読んでもらえるようにサイトを設計してきましたが、これからは「生成AIにとって読みやすいサイトにする」といった工夫が求められる時代になるかもしれませんね。
自社展示ブースで開催された「web professional summit by Orizm」
ちょっと株式会社の展示ブースでは、Web業界を牽引する制作会社を招き、各社の最新事例を聞くセミナー「web professional summit by Orizm」が3日間にわたって開催されました。ここでは2日目の模様をご紹介します。
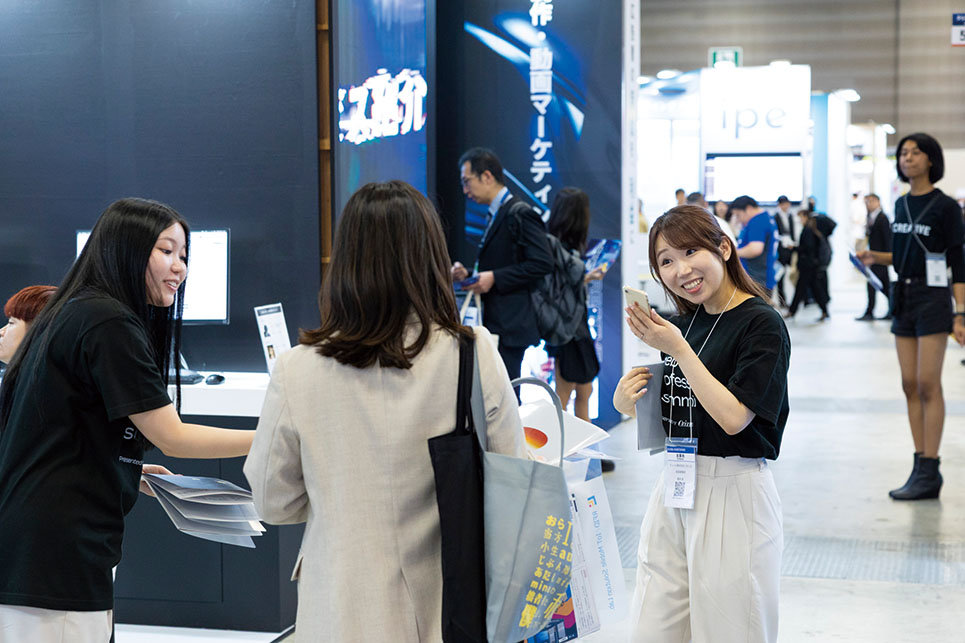
Session 1|33,000ページ・編集者720名 大規模教育サイトリニューアルの舞台裏

キテレツのカイトさんが登壇したセッションでは、学習塾「京進グループ」のWebサイトリニューアルプロジェクトが紹介されました。
対象となったのは、中高受験や語学スクールなど8ブランド、約3万3,000ページ、編集担当者720名、管理グループ70以上という、大規模かつ複雑な構成のWebサイトです。しかも全ブランドが1つのWordPressサイト上に構築されており、管理画面の「固定ページ」には膨大な数のページが並び、管理運用に大きな負荷がかかっていました。これを、ブランドごとのサブドメイン型マルチサイトに再構築することが最大の課題でした。
「開発にはWordPressのマルチサイト機能を採用しましたが、重要なのは“どう開発するか”という点です。単一のリポジトリ内で複数プロジェクトを統合する開発環境を管理するため、パッケージマネージャーにはpnpmを使いました。また、デザインの段階から実装時のクラス名を想定し、コンポーネントやカラースキームを構築するなど、全体を見通した設計が求められました」(カイトさん)
また、複雑な編集体制に対応するための承認フロー機能は、既存のプラグインを使わず、独自に開発。ポイントは、早い段階でプロトタイプを組み、顧客に実際に触れてもらうことだったといいます。
大規模サイトの再構築に挑んだリアルな経験からは、多くの示唆に富んだ知見が語られました。
Session2|クライアント・クリエイター・エンドユーザー 三者それぞれの視点と価値観の(良い意味での)ズレをどのように活かすか

スタジオスプーンの中村さんは、クライアント・クリエイター・エンドユーザーという、制作物に関わる三者の視点や価値観の「ズレ」に対する考え方を、自身の体験や制作事例から語りました。
中村さんは以前、ある企業のブランドサイトにおいて世界観の表現に重点を置きすぎた結果、繊細なアニメーションとストーリー重視の表現は実現したものの、公開後1年を待たずにリニューアルされた経験を振り返っていました。クリエイターや企業担当者にとってブランドの世界観表現は重視したい一方で、そこにこだわりすぎると、ビジネスに必要なPDCAサイクルや運用性を損ねることになりかねません。
「それぞれの立場、役割、価値観等の違いからズレが生まれると、本来必要のない部分で多くの時間や心を費やす状況が起きてしまいます。そのズレを埋めるコミュニケーションの醸成が、私の役割だと考えています」(中村さん)
近年の制作事例として紹介された「BOTANIST」ブランドサイトは、世界観の表現と、成長に応じた拡張が可能な柔軟さを兼ね備えた設計が特徴です。
中村さんは、対話を重ねる中で生まれた「ズレ」は解消すべきエラーではなく、掛け合わせて化学反応させるべき「余白」だと捉え、余白を生かすコミュニケーションをスタジオスプーンの強みにしていきたいと述べました。
Session 3|モダンなフロントエンド技術でビジネスの未来を拓く

ちょっとの小島さんは、ブース内でデモ展示されていた次世代Webサイト構築プラットフォーム「Orizm」の概要を、このセッション内でも改めて紹介しました。
Orizmは、同社が得意とするフレームワーク「Next.js」を用いたサイト開発の中で蓄積されたノウハウを集約し、パッケージ化したCMSです。“データ型”と“単独型”の両方のページを効率的に管理・更新できるほか、管理画面の柔軟なカスタマイズや外部システムとの連携が容易である点も特徴で、現在大規模サイトを中心に導入事例が増えています。また、Web開発者向けに開発環境を提供する「Orizm Developer Program」も開始されています。
同社は現在、生成AIによるページ構築機能の開発も進めており、会場では実際にプロンプトを入力してWebページをリアルタイムで生成するデモが披露されました。
「生成AI機能を開発する目的は、新規サイトの制作というよりも、大規模サイトのリニューアルをより簡単に行えるようにすることにあります。私たちはWebサイトのモダン化を通じて、お客様のビジネス成長に貢献することを、Orizm開発の大きな目標としています」(小島さん)
ページ数が多い、管理データが複雑、更新頻度が高いといった、大規模サイトならではの課題を解決できることがOrizmの強みです。生成AIの導入によって、これらの課題をさらに効率的に解消できることが期待されています。

Text:笠井美史乃 Photo:山田秀隆
