「売れてるECサイト」は何が違うのか? その理由3つの側面から考える(3/4)●特集「EC再強化」
「アクセス解析」で顧客の悩める心を掴み取る
最近では「カスタマージャニー」(顧客がどのように媒体に接触し、購入に至ったかの流れのこと)がどんどん複雑になっている。例えば、テレビで商品を見て、その詳細をスマートフォンでチェック、口コミを確認してから実店舗を訪れ、迷いに迷った末に「Instagramを見て決めた」‥‥などという事例も珍しくない。購入までのステップが、複雑化しているのだ。
「アクセス解析」はこれらすべてではなくとも、ユーザーの行動の様子を観察することができる仕組みだ。アクセス解析を徹底的に行うということは、「マーケティング(売れる仕組みづくり)」をするといこうことであると同時に、顧客が安心して、心地よく買い物できる環境を作り出す、ということでもある。
アクセス解析の結果を漫然と見ていても効果は少ない。どのようにカスタマージャニーが起き、どう購入されているのかに注目してチェックをするのだ。そのチェックのもと売れる仕組みづくりを行っていこう(01)。

アクセス解析を徹底的に使い、どのようにカスタマージャニーが起き、購入されているのかをチェックする必要がある。データをもとに仮説を立て、それを実行、そしてまたデータを取得する。その積み重ねが重要だ。
エンゲージを生み出すSNSの「Conversation(会話)」を活用せよ
ソーシャルメディアがここまで成長発展すると、もう無視することはできない。購入前にソーシャルメディアで店の評判を確認する人が急増しているからだ。
「顧客の声」には「ベネフィット(顧客利益)」が書き込まれることが多いが、このベネフィットを有効活用したい。「当社のECサイトに声を掲載させてほしい」「ソーシャルで紹介したい」と、顧客の声に返信することで、直接的な会話が生まれやすい。アメリカではこれを「Conversation Commerce (会話による販売)」と呼んでいる。日本でもメールやチャットのやりとりが、購入につながる事例が昔からあるが、これがソーシャルメディア上で行われているのが最近の事例だ。数年前であれば、ソーシャルメディア上でEC店舗と個人がやりとりするなどあり得ない感じだったが、最近はごく普通になった。
Conversation Commerceを進めているEC店舗は顧客を安心させ、エンゲージ(つながり)を作りあげている(02)。
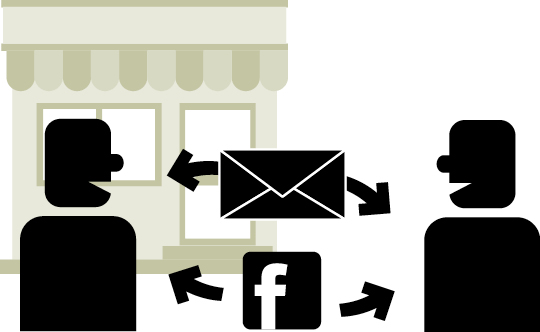
メールやチャット、さらにはソーシャルを活用するのは、顧客との接点を強めるための鍵になる。
「A/Bテスト」で、刻々と移り変わる顧客の「好き」を探り出せ
現在、EC店舗で使用されている商品画像は、これまでの経験を踏まえた、さまざまな仮説と実証をもとにして作られた画像だろう。先輩から“伝承された”フォーマットを使ってデザインされたものを使っている方も多いのではないだろうか?
商品画像にキャッチコピーを加えたり、モデルを入れてみたり、さらには「文字は左に入れたほうがよい」「ボタンは○色がよい」などといった感じで、試行錯誤をしてきたはずだ。最近は「売れる画像」の定番を紹介する記事も多いが、実は、スマートフォンの登場でその「定番」がわからなくなっているのだ。
そこで使われるのが「A/Bテスト」だ。最近では、中小企業でも取り組んでいるところが増えてきており、ツールを使ったり、手動で確認している人もいる。商品画像がシンプルな方が良いのか、キャッチコピーはどこに入れたほうがいいのかを少しずつ入れ替えてチェックすることで顧客の「今」の好みを探り出そうというわけだ。
ちなみにA/Bテストの結果には、「えっ?」と驚かされることが多い。特にデザイナーにとってはショックな結果につながることも少なくない。先輩から伝承されたフォーマットが否定されることもあるだろう。だが、時代は刻々と変化する。仮説の実行検証を重ねることで、顧客の好みをサイトにしっかりと反映させるのだ。
「モバイルゲドン」不発が教えてくれた技術との正しい向き合い方
今年の2月、Googleが「スマートフォン対応をしていないサイトは検索順位を落とす」といったコメントを発表し、業界の一部が混乱するという出来事があった。その時に囁かれたのが「Googleが推奨しているレスポンシブデザイン(どんなデバイスから見ても、共通のコンテンツを見ることができるようにしたデザインのこと)でなければNG」といった噂だ。これを映画『アルマゲドン』とかけて「モバイルゲドン」などと、事態を警戒する声が上がったのだ。
しかし、施策が実行された4月21日には、ほとんど何も起きなかった。モバイル対応していないサイトが、そのまま上位に残るといったケースさえ見受けられた。
これに対してGoogleは、「皆さんのサイトがスマートフォン対応しているので結果はあまり変わらなかった」とコメントを出しているが、実際のところ、Googleの言うモバイル対応とは、もっとモバイルフレンドリーなWebサイトを検索結果に出したいという狙いがあったようで、サイトのモバイルユーザビリティ問題も、Googleサーチコンソールで確認できるようにしていた。必ずしも、レスポンシブ対応していなくても、より上位の概念と考えられる「アダプティブデザイン(どんな媒体でからも同じ体験が得られるようにつくられたデザインのこと)」に対応している会社はきちんと評価されている。
Googleの影響はとても大きい。検索からの流入はとても大切だからだ。しかし、小手先の対策にばかり目をやっていてはダメだ。大事なのは情報が真実であり、新鮮であることなのだ。
3年後には「レスポンシブデザインって、何だっけ?」となっていると思う。その時に大切なことを失っていては身も蓋もない。

- Text:川連一豊
- フォースター株式会社代表取締役、ジャパンEコマースコンサルタント協会代表理事。1999年よりEコマースを始め、倍々で業績を伸ばす。楽天市場で講師等を手掛けた後独立。これまで1万社以上の企業、モール、ECサイトにアドバイスや取引実績がある。
