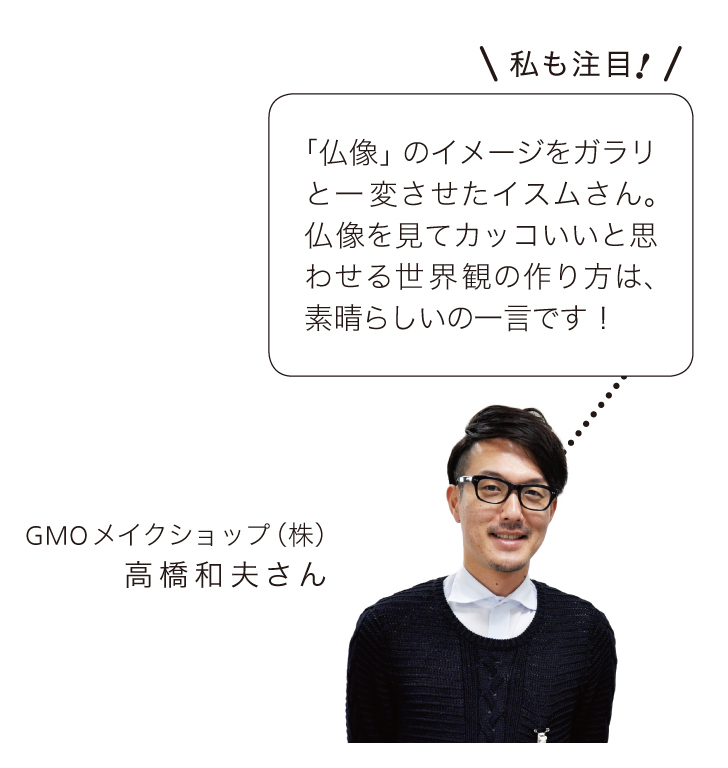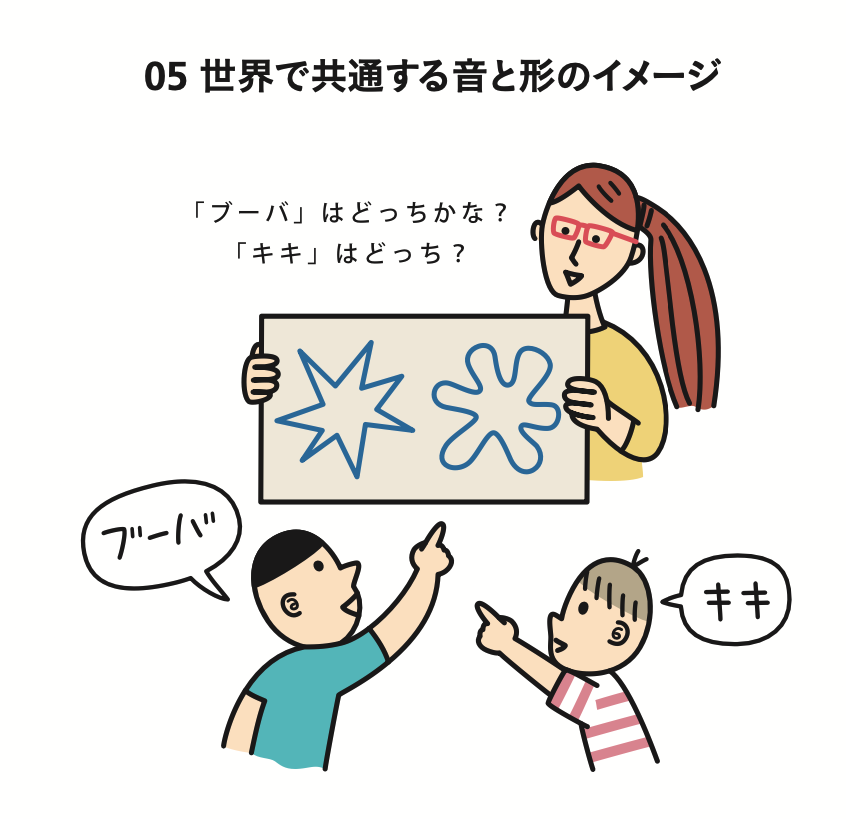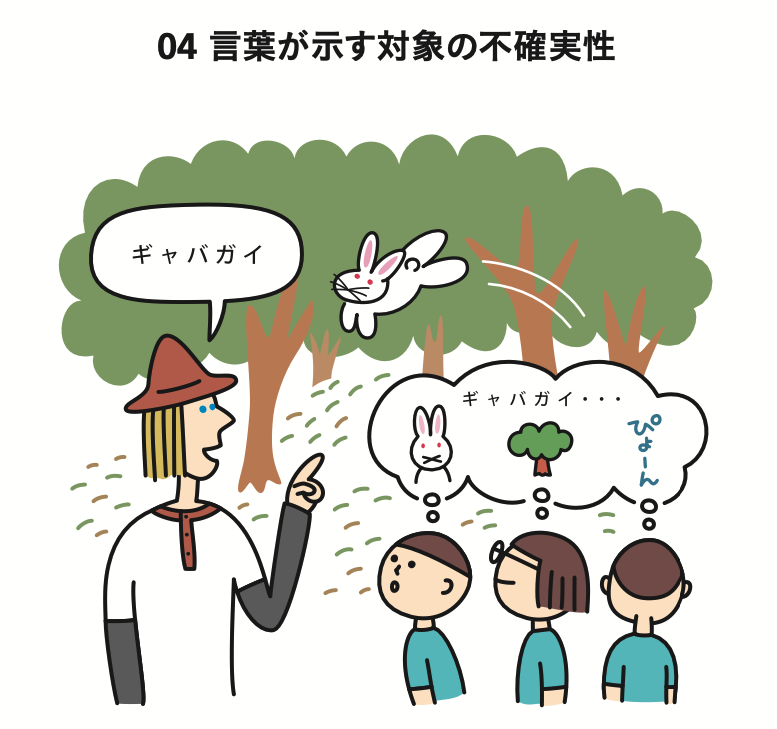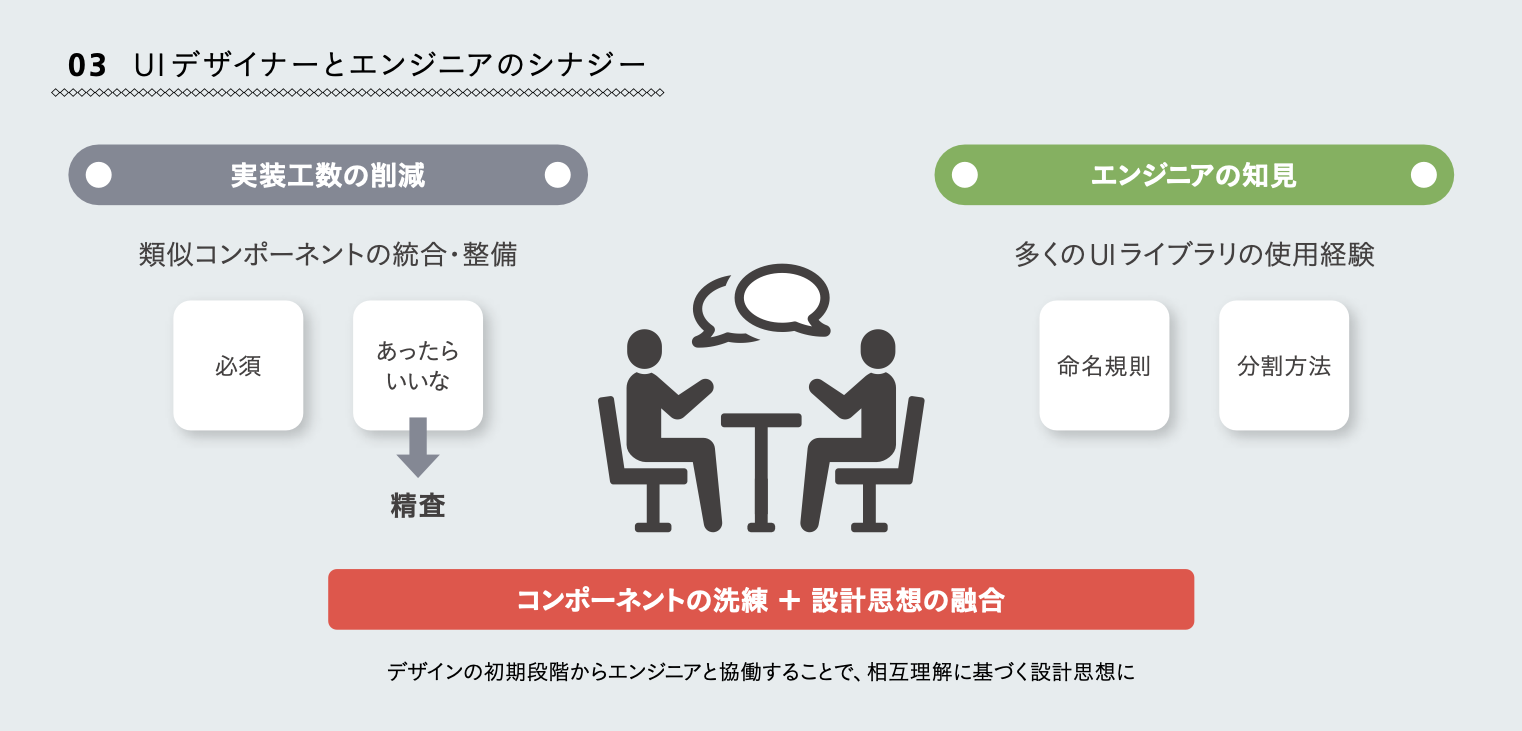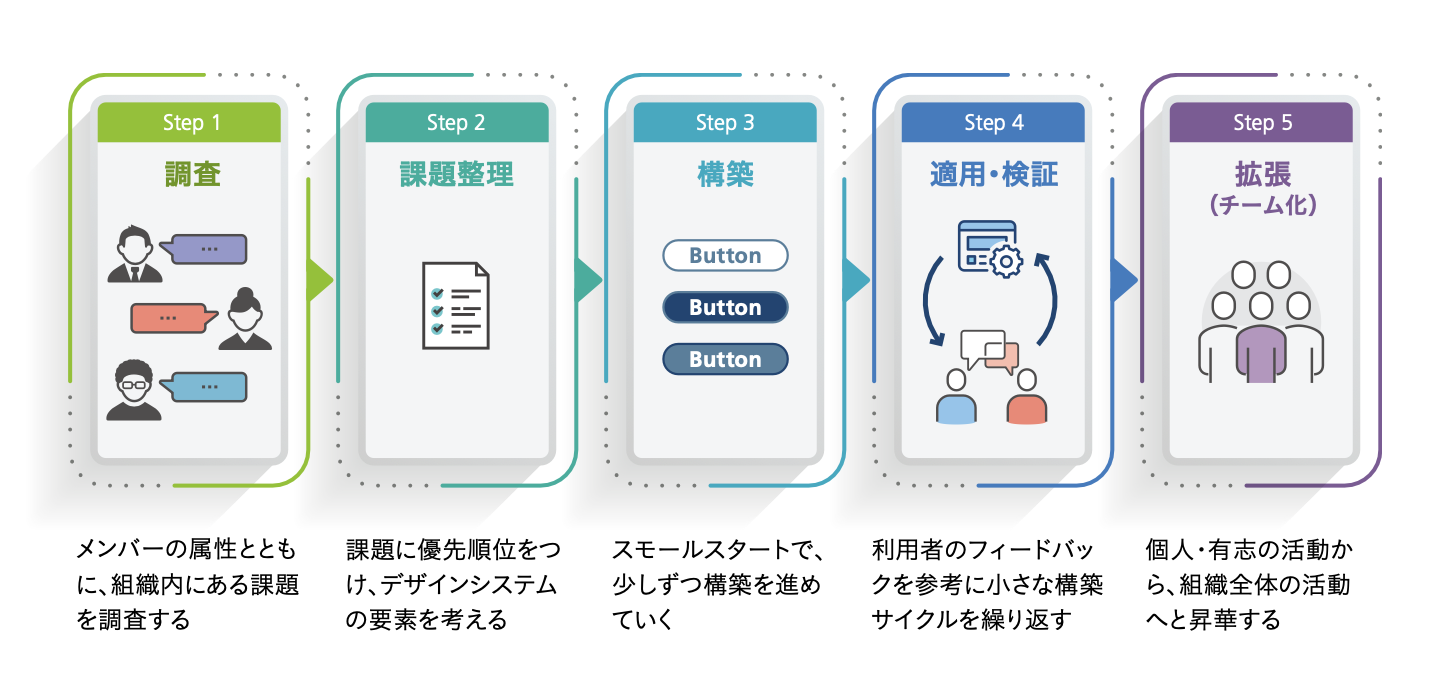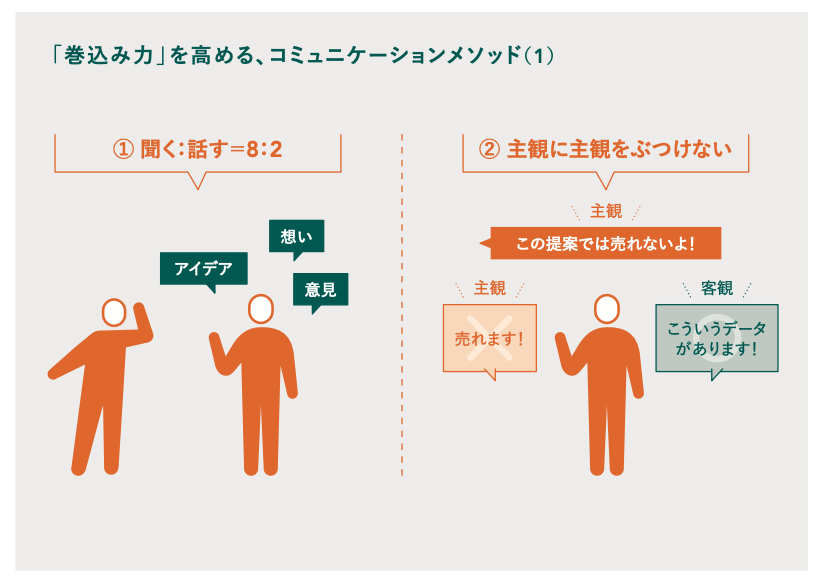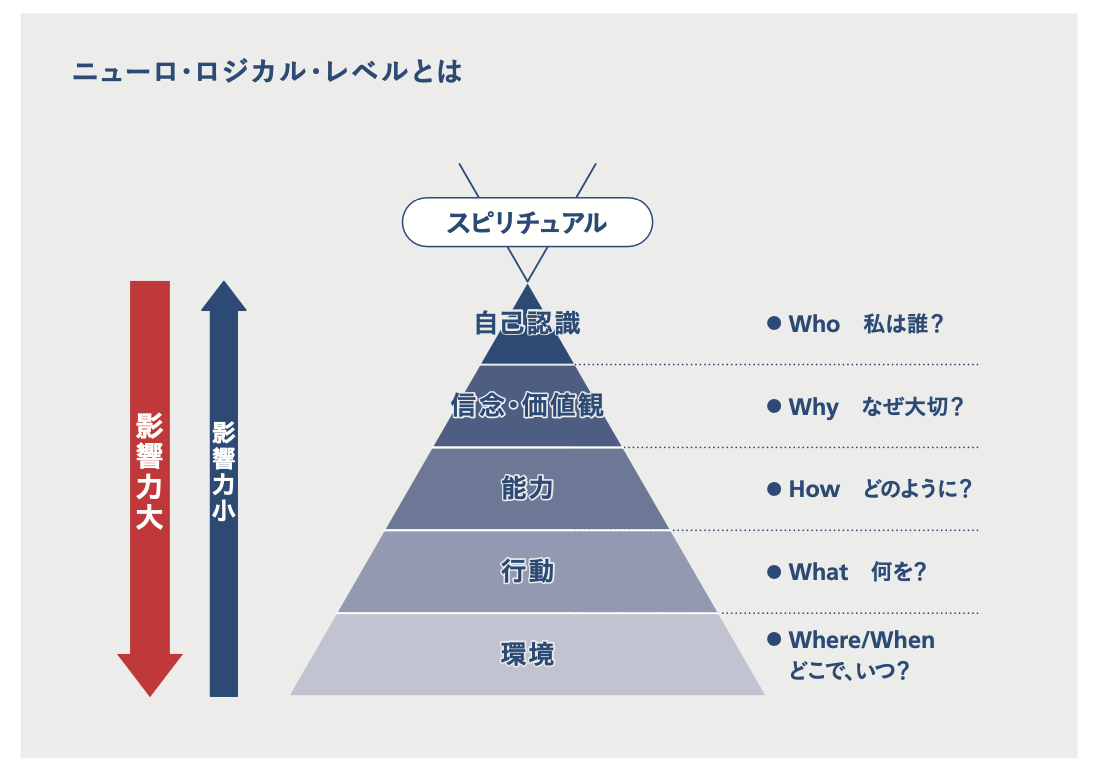インテリア仏像という新しい価値観の提案で市場を作り出す「イスム」

創業:2011年4月8日
スタッフ数:17人
取扱商品:仏像フィギュア
商品点数:約40点
SNS:Facebook Twitter Instagram
存在しない市場を生み出すためのブランディング
「イスム」は、仏像をインテリアとして楽しむことを提案するブランドだ。もともと仏像や七福神などの縁起物を販売していた会社MORITAが、2011年に立ち上げた。その経緯をブランドマネージャーの松川政輝さんはこう話す。
「弊社の社長が、仏像をアートとして見るのは面白いんじゃないかと目をつけ、イスムの元となるような商品開発を2006年から始め、2007年に最初の商品が発売になりました。でも最初はぜんぜん売れなかったんです。一番障害となったのは、仏像を一般向けに販売するという市場が存在しなかったことです。百貨店に置いていただくにしても、どの売り場が適切なのかわからないし、どのバイヤーさんに話をすればいいのかもわからないという状況でした。ただ現物を見せるだけではダメで、仏像がカッコイイということを知らしめて、市場を作らなければいけません。そこで、『インテリアやアートなオブジェとして楽しむための仏像』というコンセプトをしっかり決めて、2011年にイスムというブランドを立ち上げました。2009年に仏像ブームが来たので、その波に乗れたというのも追い風になりました」
現在では、ネットショップや直営店で販売するほかに、全国の百貨店でも取り扱われている。
「店舗によってインテリアコーナーに置かれたり、食器と並んでいたりします。また、いまもやっているのですが、日本全国津々浦々の百貨店さんなどで催事をさせていただいて、そこで新しいお客様との接点を作っています。安い価格帯の商品ではないので、以前から知ってはいても実際に見てから購入したかったというお客様もいらっしゃいます。なかには『地元に催事がくるのを待っていたよ』とおっしゃって、すごい量をまとめてお買い上げになった方もいらっしゃいました」
イスムの仏像は、石粉に樹脂を混ぜて固めたポリストーン製で、細部まで丁寧に作られている。そうした技術力の高さも強みだ。
「実在する仏像のレプリカなので、基本的には実物を忠実に再現しています。ただ、インテリアとして美しく見えるように、たとえば頭身の比率をわずかに変えるなどのデフォルメはしています。ネットショップでは、こうした商品の良さや特徴を平面でいかに伝えられるかということに注力しています。以前は商品のディテールがよくわかるほうが良いと考え、白背景で撮影し、かなり拡大表示して見られるようにしていました。しかし、それでは部屋に置いたときの雰囲気が伝わりづらいと考え、1年ほど前に、ハウススタジオで落ち着いた照明で撮ったものに写真を差し替えるなど、試行錯誤しています」

イスムのネットショップは、他のチャネルを含めた全売り上げの中で、金額ベースで25%を占める。商品ページには、造形のこだわり、モデルとなった仏像の紹介、モチーフとなった仏の背景などの情報が書かれている。こうしたウンチクを知って、楽しみがより深くなるのも仏像の特徴といえる。写真はさまざまなアングルからのカットのほか、部屋に置いた雰囲気のわかるものが用意されている
実店舗の効果とリピーター率50%越えの顧客
イスムの客層はどのような人が多いのだろうか。
「50代から70代の男性が多いです。プラモデルのような感覚で、男性のほうがこういったものを好きな方が多いんでしょうね。ただ、表参道店では実際に来店されるのは女性のお客様が多いので、今後は女性の感性に訴えかけるマーケティングをしていかなくてはと思っています」
2013年に11月にオープンした表参道店、2015年4月にオープンした谷中店と、現在は都内に2つの直営店を構える。

「店舗はショールーム的な意味合いが大きいです。もちろん店頭で買われる方もいらっしゃいますが、重たいので実物を見て気に入ったらネットショップで買われるという方も多いですね。認知されるきっかけになったり、メディアの方に取材されやすくなったり、お客様に信用をしてもらえたりと、販売すること以外のメリットが多くあります。実際に、店舗ができてから弊社直販の販売率は増えています」
リピーター率が非常に高いのも特徴的だ。
「お客様の半数以上がリピーターの方です。特定の仏像が大好きという方はそれだけを買われて満足されますが、そこから一歩踏み込まれた方は、仏像への興味がどんどん増していくのかなと思います。そうしたお客様のロイヤリティを高める取り組みもしています。たとえばポイントシステムは直営店とネットショップで共通化していて、貯めたポイントは購入費として使えるだけでなく、非売品アイテムと交換もできます。また、お客様がイスムのアイテムを部屋に飾った写真を投稿してもらう、『インテリアフォトコンスト』を毎年開催しています。ものすごくたくさんの応募数があるわけではありませんが、ニッチなマーケットだからこそ、こうした小さな取り組みが大きな意味を持つと思っています。今後ももっと深く楽しめるようなコンテンツを発信し続けていきたいです」

ネット広告の有用性と海外進出を踏みとどまる理由
既存顧客との関係構築とあわせて、新規顧客の開拓も大事な課題となる。
「イスムはネット広告が必要不可欠です。サイトを見てぱっと買うような商材ではなくて、比較的検討期間が長いため、リターゲティング広告が有効です。最初にリスティングでお客様を集めて、検討期間はリターゲティングで想起させるという二段構えでやっています。初めて購入される方のハードルがすごく高く、そこが一番検討期間が長くなりがちなところです。1つ買われると、そのあとは次に繋がりやすいんですけど」
FacebookページやTwitter、ブログなど、オンライン上の情報発信にも力を入れている。
「特にFacebookページの影響が大きいですね。百貨店さんなどでの催事にいらっしゃる方も、Facebookを見ましたという方が多いですし、ネットショップへの流入元としてもダントツ1位です。運用は広報の者が担当していて、毎日少なくとも1本は投稿するようにしています。とくに写真の力が大きい商材なので、相性が良いというのもあるかもしれません」

1月末現在で2万7,800人ものいいね!がついている。広報を兼任する担当者が管理し、催事の情報など毎日1件は投稿するようにしている。写真がとても目を惹き、各投稿へのいいね!の数も数百件と反応がよい
Facebookは全世界に伝達できるのもメリットだ。日本のトラディショナルなアートとして海外ウケもよさそうだが、ネットショップではいまのところ国内発送のみの対応となっている。
「 Facebookでは2万7,800ほどのいいね!をいただいているのですが、そのうち31%が海外の方なんですよ。実際に海外で買えないのかという問い合わせも多くいただいています。まだ対応していないのは、国外に向けて販売するならば、きちんとそのためのマーケティングを行うべきだと考えているからです。たとえばタイの方などは、金色のきらびやかな大仏が好きなど嗜好性も違いますし。とはいっても、数年以内には海外販売の体制も整えていきたいです。毎年、今年こそはと思っています」