《大阪・関西万博のデザインシステムVol.1》クリエイティブディレクター・引地耕太さんが「デザインポリシー」策定に込めた意図
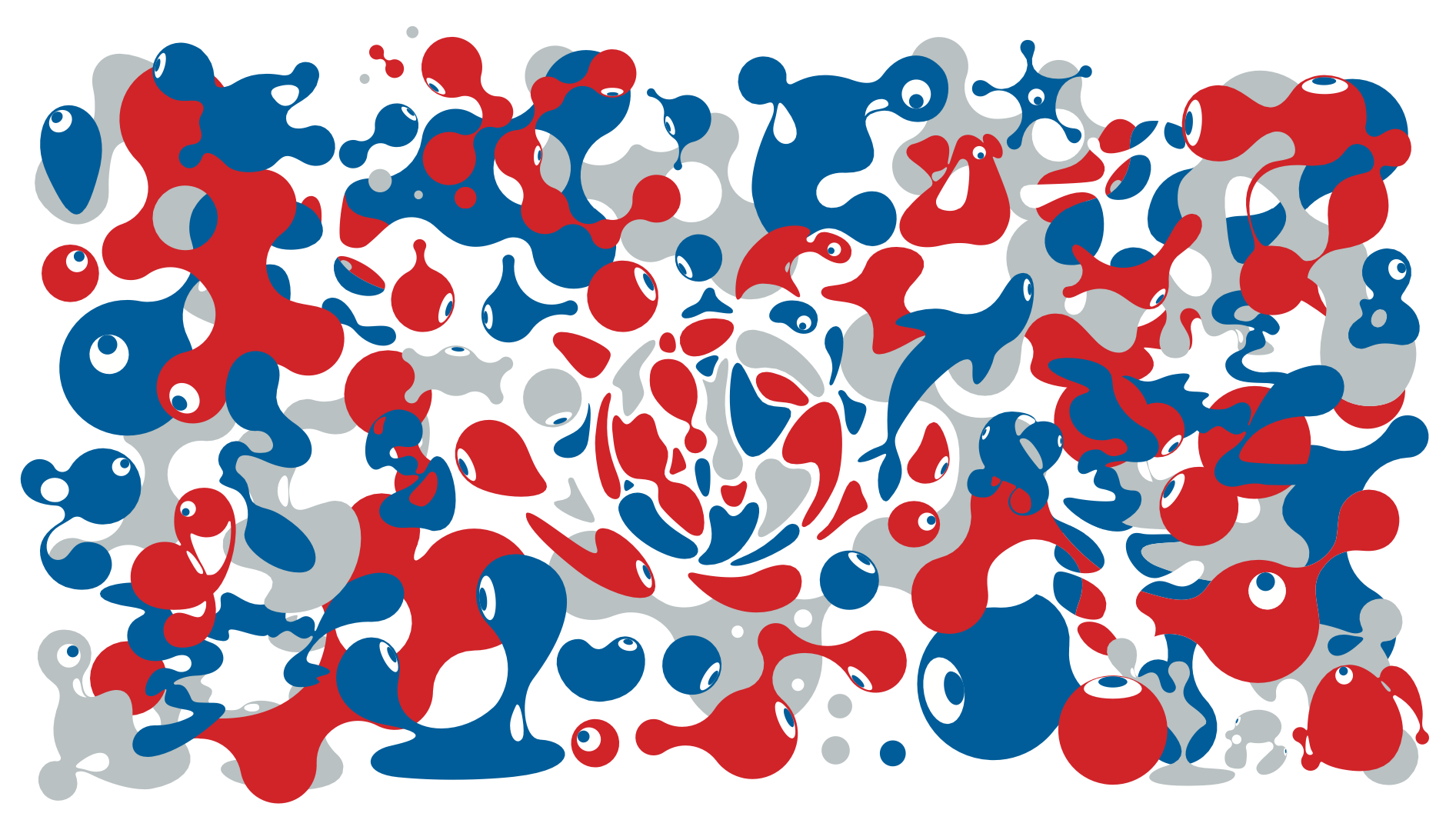
2025年4月13日に開幕した大阪・関西万博。そのVIデザインシステムを作成したのが、クリエイティブディレクターの引地耕太さん(制作当時は株式会社ワントゥーテン。現在は独立)です。Web制作業界における“デザインシステム”とは少し意味合いが異なりますが、設計に至る引地さんの思考や、提示されたコンセプトは、これからのデザイン、制作に関わる多くの方にとって、未来を考えていくためのヒントになるはずです。そこで引地さんに、大阪・関西万博のVIデザインシステム作成のプロセスについて、詳しく教えてもらいました。
チャレンジングな取り組みに デザインの持つ可能性を投げかける
大阪・関西万博VI(ロゴマークを中心としたデザインシステム開発)策定業務の企画提案公募が行われたのは、2021年11月。これに応じた企業の一つが、株式会社ワントゥーテンでした。提案に向けたプロジェクトのクリエイティブディレクター/アートディレクターを勤めたのが、当時同社に所属していた引地耕太さんです。
引地さんは、抽象的なコンセプト設計の段階から具体となる表現の方向性まで、ほとんどを自身で手を動かしながら固めていったと言います。
「私自身がデザイナー出身ということもあり、コンセプト設計をしながら具体の部分をイメージすることや、概念と具体を行き来しながら全体の世界観を構築することが自分の得意分野です。その意味でも、考えながら自分で手を動かすのはとても自然なことです。手と脳はつながっていて、思考を深めるためにも手を動かすことが必要なのです」(引地さん、以下同)
最終的にデザインシステムの形に完成させる過程では、ワントゥーテンのデザイナーやCTO、社外のエンジニア、モーションデザイナーなどが加わっています。引地さんのコンセプトには、グラフィックだけでなく、プログラミングやモーションも必要だったのです。そこへ至る過程を辿っていきましょう。
「2025年日本国際博覧会」(略称「大阪・関西万博」)とは?
大阪市臨海部「夢洲(ゆめしま)」を会場に、2025年4月13日~10月13日まで開催される国際博覧会。世界的な危機や社会課題を乗り越えることを目指し、多様な価値観の交流と、新たなつながりや創造を促進していく。国や大企業だけでなく、中小の企業・団体、市民による展示や活動をサポートするプログラムも多数。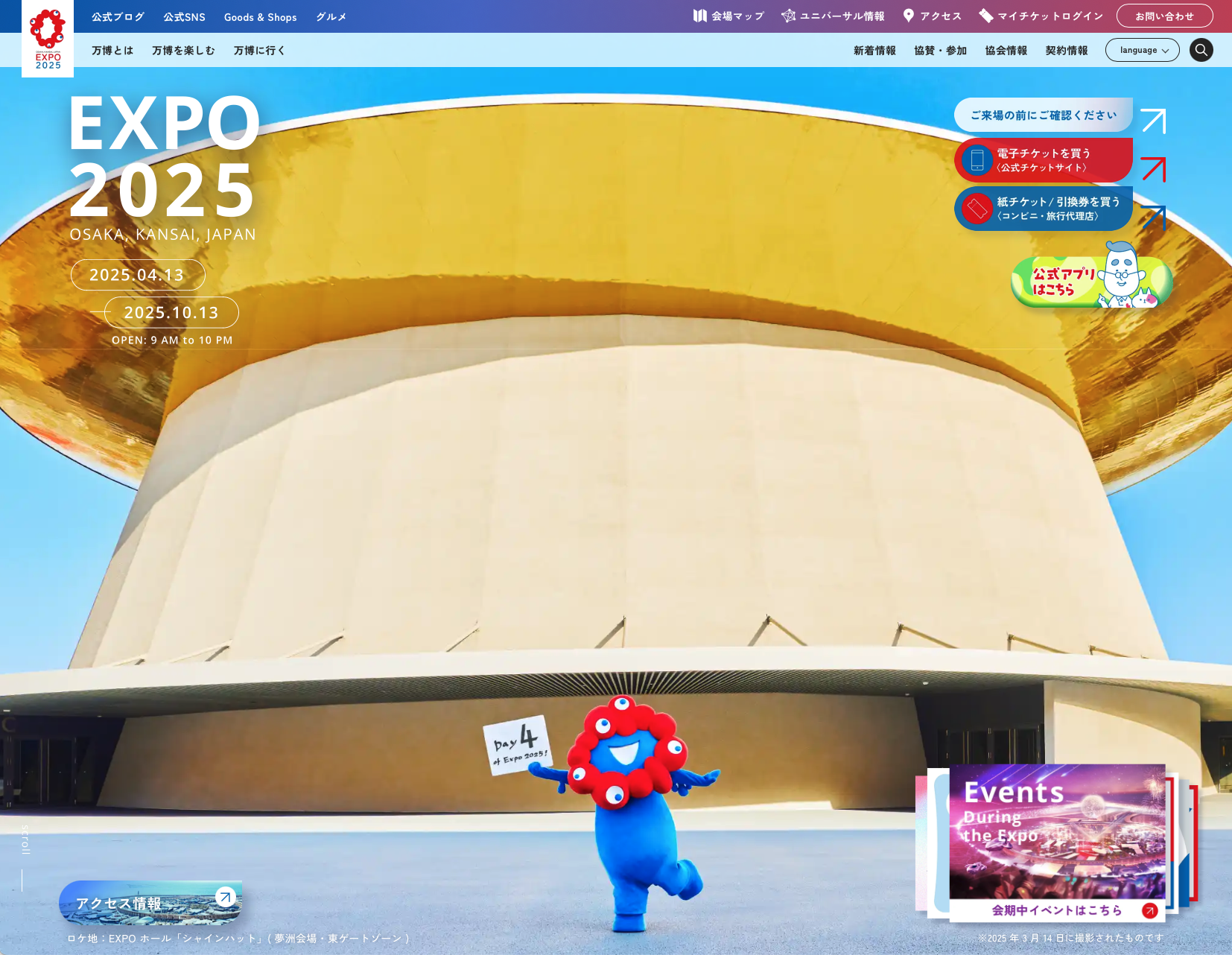
VIデザインシステム自体が 万博の持つメッセージを内包するものに
VIデザインシステムというと、一般的にロゴの使用や印刷物、サイン等への展開に関するガイドラインを想像します。しかし引地さんは最初に、システムそのものがこの万博の持つ哲学やメッセージのようなものを内包するものにできないかと考えました。
「万博のテーマに“デザイン”という言葉が入るのは今回が初めてだと聞きました。それはデザイナーとして、とてもポジティブなことに感じられました。社会におけるデザインの意味や役割が広がりつつある中で、大阪・関西万博はデザインにどう取り組むのか。とてもチャレンジングなことだと思います。そこにどんな可能性があるのか。私たちデザイナーはどうしていけばいいのか。そうした問いかけのようなものをデザインシステムに取り込めないだろうか。それが当初から考えていたねらいの一つです」

この考えを土台に、次に万博の全体像に対する理解を深めていきました。大阪・関西万博にはテーマと同時に「People’s Living Lab(未来社会の実験場)」というコンセプトがあります。
80億人がアイデアを交換して世界の課題を解決していく、未来社会を共に創っていく、万博をその実験場に位置付けようというものです。科学技術や産業を通して国が力を見せあう祭典から、社会・世界・地球全体で私たちが何をしていくべきかを確かめる実験場へと、万博の性質が変化しているのです。さらに、理念として「持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献」「日本の国家戦略Society5.0の実現」が掲げられています。
また、VIはロゴとどう関連させるかも重要な要素です。公募で採用されたインパクトのあるロゴは、細胞が集まって円を描くことで命の輝きを表現しています。引地さんはこうした点に注目していきました。
これらを踏まえてどのようなデザインシステムを構築すればいいか。実際に形にしていく前に、引地さんはその方針となる5つの「デザインポリシー」を書き出しました。

目指す哲学、戦略を言葉で示す 5つの「デザインポリシー」
デザインポリシーの策定は、公募要件に含まれていたわけではありません。しかし、あえて策定したことには理由がありました。
「1970年の大阪万博でも、デザイン評論家の勝見勝氏を中心にデザインポリシーが設計さました。それを紐解いてみて、自分たちが目指すべきものに対する哲学、あるいは戦略のようなものを明文化して共有することが、デザインシステムにとって非常に重要なのではないかと考えたのです」
デザインシステムは、デザイン要素を統一された形で使うためのルールではありますが、何を目指してそうなっているのか、多くの人に理解してもらうために言語化の必要性を感じたのだと、引地さんは言います。また、先輩たちへのリスペクトを示しながら、それを今の時代にアップデートするならどうなるか、ビジュアルでなくまず言語で示していくことが、過去からの文脈をつなげる意味で大事なことだったとも語りました。
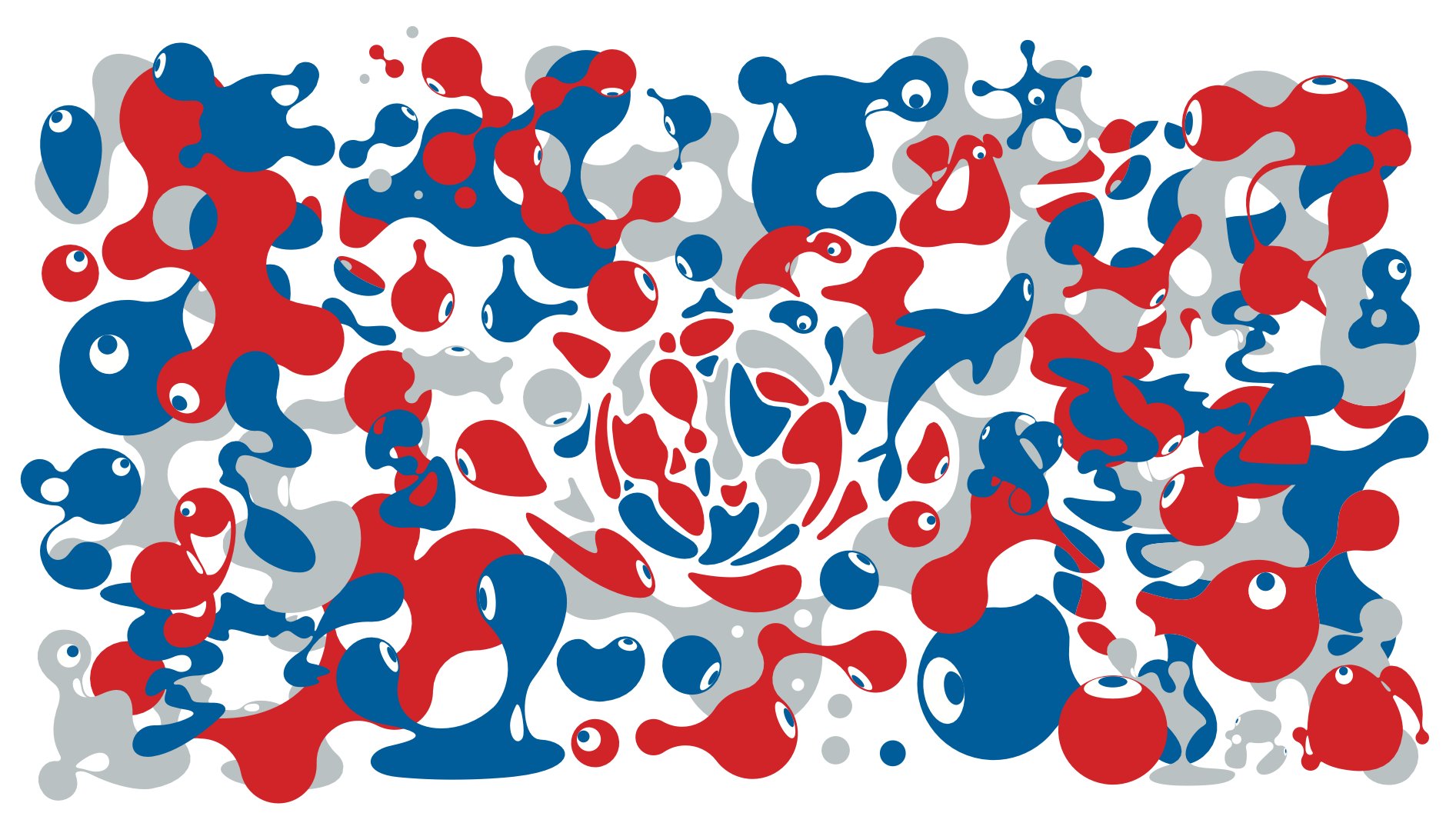
プロフィール

引地耕太さん
クリエイティブディレクター/アートディレクター/教育者。1982年鹿児島県生まれ。株式会社 VISIONs 代表 / Co-Futures Platform『COMMONs』代表。タナカノリユキアクティビティ、デジタルエージェンシー1→10にてECDを務め、2025年起業。現在は東京/福岡を拠点に、ブランド戦略とイノベーション創出を専門にデザイン/エンターテイメント/広告/アートなど領域を越境し活動。大阪・関西万博におけるブランディングのためのデザインシステムを手掛け、現在はデザイン・アート・サウンドを統合し夢洲会場全体を彩るオープンデザインプロジェクト「EXPO WORLDs」のクリエイティブディレクターを務める。
Text:笠井美史乃、協力:2025日本国際博覧会協会
※本記事は「Web Designing 2024年4月号」に掲載した記事を一部抜粋・再編集したうえで掲載しています。
《続きはこちらから》
・Vol.2|引地耕太さんが“3つのエレメント”で表現したかったものとは?
・Vol.3|引地耕太さんが考える“共創”の価値「デザインは、社会を動かす“武器”のようなものになってきている」
