原研哉が生み出す広告ビジュアルは、なぜ「語りかけてくる」のか? 言語化スキルを鍛える、言葉の“連鎖トレーニング”
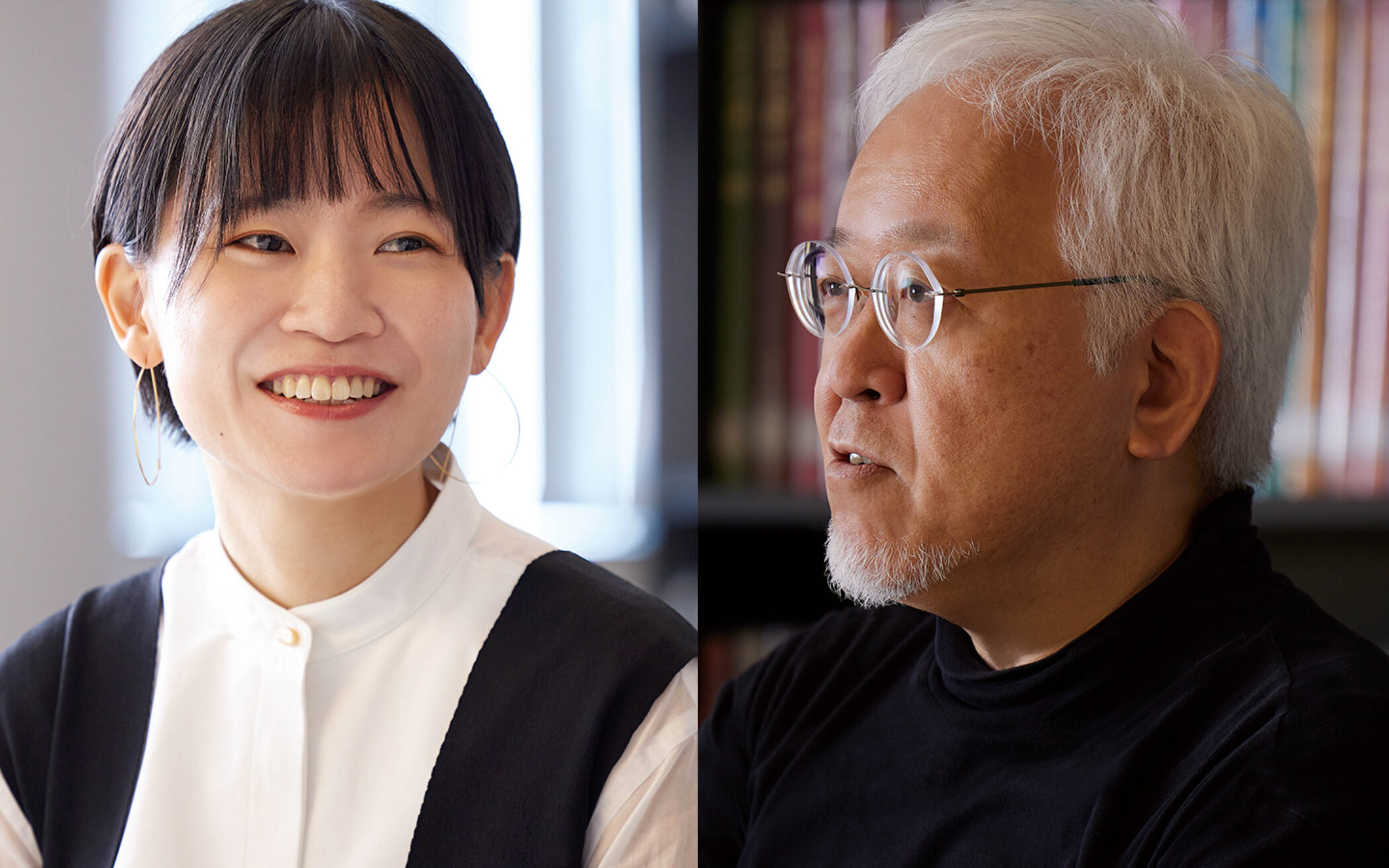
制作の現場では、提案の場で、あるいは成果物に対して、デザインを言葉で説明することを求められる機会が増えています。デザインの文脈から見た「言語化」とは、さらに「言葉」とはどのようなものなのか。著書等で繰り返しデザインを論じてきた原研哉さんに、言語化を探求しながら現状に疑問も持つ小玉千陽さんが聞きます。(前後編の後編)
閉じ込められた言葉の
可能性を再発見する
原研哉(以下、原) 小玉さんは、日頃どんなものから言葉を得ることが多いですか? 自分にとっての言葉に対する感受性を鼓舞されたとか、どんな言葉を“食べて”いるか、ということでいうと。
小玉千陽(以下、小玉) そうですね、やっぱり昔から本を読むことです。紙の本や雑誌なども好きですが、そうは言ってもこのご時世ですからインターネットでも膨大な情報を見ています。
ただ、あくまで情報としてインプットするよう割り切って、そこと距離を置いて小説やエッセイを読んでいる時のほうが、言葉を「いただいている」と感じます。
原 広告コピーはどうですか?
小玉 すごく好きです。小学生の頃に広告コピーを自由研究のテーマにしました。なぜこのたった5文字のコピーが小学生の自分にもこんなに響くのだろうと思ったことが原体験にあります。
原 僕は駆け出しの頃、糸井重里さんや仲畑貴志さんのコピーを見て、本当にうまいこと書くなと思っていました。最近そういうコピーも少なくなってきたので、若い方はどんなところからインスピレーションを得ているのだろうと思っていました。

小玉 それでいうと、私より下の世代のスタッフはSlackなどでも絵文字をポンポン送ってコミュニケーションを取ってくるんです。リアクションもスタンプで。それが「このタイミングでそのスタンプを返してくる! なかなかやるね」と思わせる使い方で、これはちょっと向き合わなくてはならないと思いました。
スケッチでも言葉でもない、絵文字という記号化されたものに対する価値観に寄り添っていかないと、彼らとコミュニケーションを取れなくなるのではという、伝える側としての危機感が少しあります。
原 僕は内心、絵文字を使いたいと思っている(笑)。だけど、ちょっと控えておこうかなと。それは、他人が考えた絵文字は他人の道具を使っている感じだから。もし僕が20代だったら、友人とのコミュニケーションには自分の絵文字シリーズをつくるだろうと思います。
人が持つ言語モデルは
多次元的な言葉の連鎖
小玉 私は、デザインしたり物事を考えたりする時に、具体と抽象を行き来する軸と、地上0mと鳥瞰を行き来して対象を見る軸の2つを基準にすることが多いのですが、言葉はどうしても具体寄りで地上0mに行きがちです。
でも原さんの言葉は、抽象寄りで鳥瞰していることが多く感じられて、どうすればそうなれるのかをお聞きしてみたいと思っていました。
原 何でしょうね……。僕はあまり頭がよくないから、自分のわかっていることは人にもわかるだろうという自信があります。天才は直感的に真理をわかったりするから、それを人に伝えることはなかなか難しいのですが、僕は割と平易な頭脳なので、自分が把握していることなら噛み砕いていけばちゃんと伝わると。
だから文章もなぜか2度繰り返していることが多い。「Aである、つまりこういうことだ」「Bである、別の言い方をするとこうだ」という、1本ではわからないものを複線にすることで理解を担保し、次に進んでいくのです。その繰り返しがくどくなくつながる時は、いい説明ができたと思いますね。
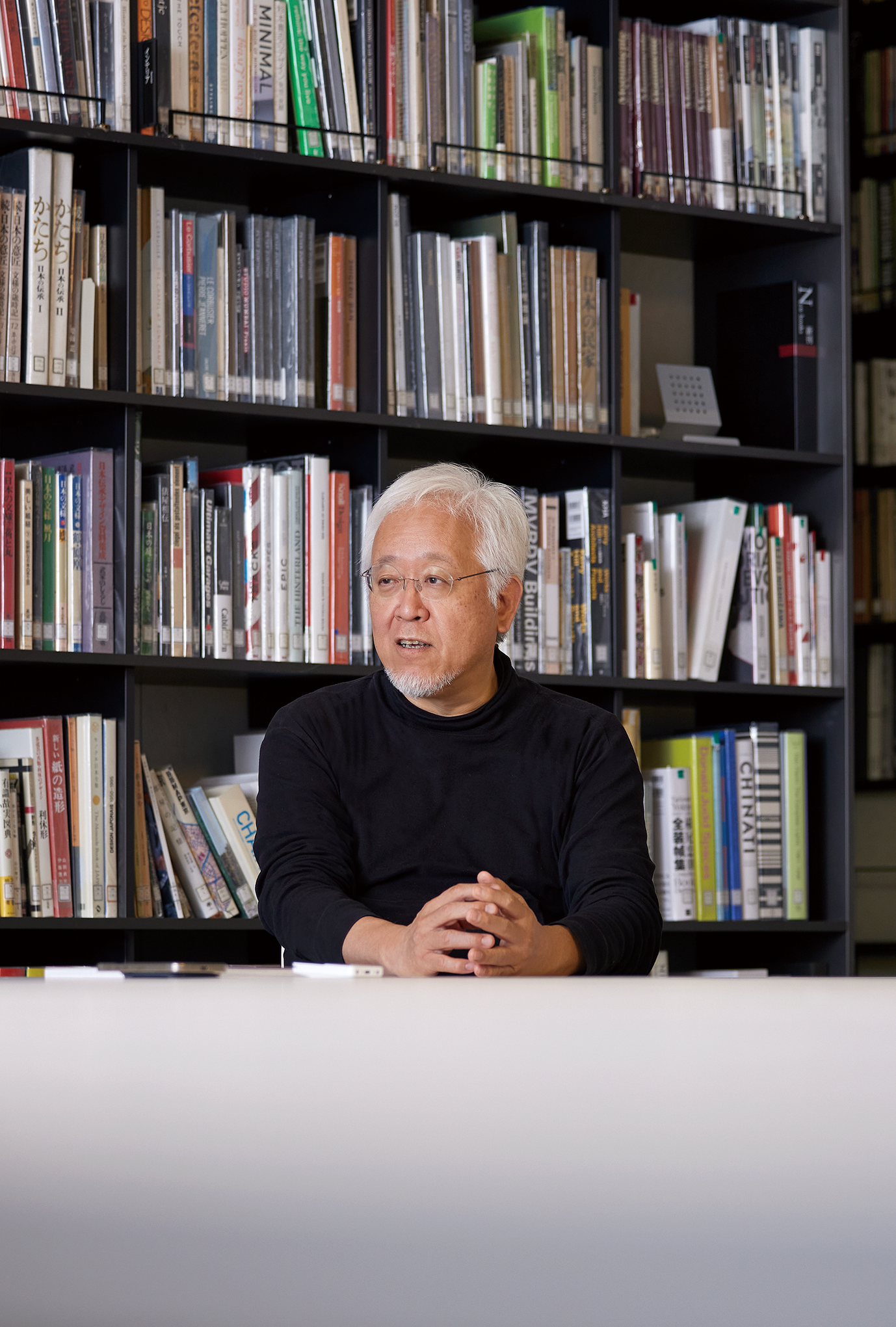
小玉 それはどなたかに教わったことですか?
原 教わってはいないです。ただ、(日本デザインセンターの)若いコピーライターが本田勝一さんの『日本語の作文技術』(朝日文庫1976年。新版は2015年)を読んでいるのを見て思い出したのですが、言葉の使い方に関する本は学生の頃からいろいろ読んでいた気がします。
本田さんは「体言止めは下品」と書いていたように記憶しています。そういった言葉に関する小さな断片が、今でも自分の中のいろいろなところに残っています。そういう意味では、言葉が好きだったんでしょうね。
小玉 そうなんですか。どうすれば原さんのような「言語化」を身につけることができるか、ずっと気になっていました。
原 言語とは一体何なのかと考えたとき、僕はイメージの連鎖だと思ったことがあって、学生時代にその“連鎖”をつくってみました。六角形の網の目が、ずっと続いているとしましょう。1つの六角形の真ん中に名詞を1つ、例えば「夏」と入れます。その周りに6つの六角形がある。そこに「夏」を取り巻く6つの名詞を入れる。例えば「西瓜」「冷蔵庫」「風鈴」などです。
それが綺麗にできたら、次は六角形の各頂点に、名詞を修飾する形容詞を入れていきます。そうすると、1つの名詞を6つの形容詞が囲み、1つの形容詞を3つの名詞が囲むという連鎖ができますよね。これをずっと続けていく。なかなか語彙が鍛えられます。
小玉 六角形の間に入れる形容詞は被ってはいけないのですか?
原 そうです。名詞も1回しか使ってはいけない。だから結構難しいのですが、やってみると面白い構造が見えてきます。辞書ではなく、それ自体がひとつのポエトリーのようでもあり……。夏を中心とした記憶の情景が言葉の連鎖で描き出されてくる感じです。言葉から湧き出すイメージが自然なつながりを持って広がる。こういう観念連鎖のようなものを共有しているのが“日本語の世界”なのだろうと思いました。
今話したのは二次元的な構造ですが、これが頭の中で、多次元で存在するとしたら……。言語学者のノーム・チョムスキーがいう人間の言語に共通する普遍的な文法などとはまた違う、いわゆる「観念の連鎖」が別レイヤーにあって、そこに対する感受性が言葉を使う人の背景をつくっているのではないかと思うのです。
小玉 原さんの手がけられた広告ビジュアルを見たときに、画なのに、画が語っているような印象がありました。本当にそういう風に考えられているのだとわかって納得です。
原 僕はデザインシンキングを「仮想的推論」と言っています。つまり「だったりして」と考えていくことです。
もし日本列島が今より500km南にあったらと考えてみる。あるいは、人間は都市やビル、テーブルやPCなど多くのものを四角くデザインしてきたけれど、もしそれが六角形だったらと考えてみる。こうした「だったりして」がクリエーションではないかと。
ニューラルネットワークの偶発的な発火が脳の運動だとすると、そこに論理を持ち込むことのほうがむしろ不自然かもしれません。ロジックで筋道立てることをみんなが強要しているだけで、脳はいつも散逸的に働こうとしているのではないかとすら思います。AIがロジックを緻密に遂行するものだとすると、人間の脳はそのようにはできていない。そこに言葉の可能性も思考の可能性もあるような気がします。
そんなふうに世界はまだまだ未知なものなのですから、クリエイターの言葉はそこに手を伸ばさなくては、面白くなっていかないのではないでしょうか。
(前編はこちら)
Text: 笠井美史乃 Photo: 石塚定人
※本記事は「Web Designing 2024年6月号」に掲載した記事を一部抜粋・再編集したうえで掲載しています。
