「ユカイ工学」青木俊介さんが語る、IoTの未来●特集「IoTの現在」
活用すべきは、“本体”から“環境”へ
ーー今日は、ロボット「BOCCO」をはじめとするユニークなハードウェアをリリースしているユカイ工学の青木さんにIoTにまつわる話を伺いたいと考えているのですが、本題に入る前に、まずは、ユカイ工学を立ち上げた経緯から聞かせてください。
「僕はもともとチームラボという会社にCTOとして立ち上げに関わって、主にサーバサイドの担当をしていました。検索エンジンをつくったり、いろいろなサービスのバックエンドを構築したりといったことをずっとやっていたんです。それはそれでやりがいのある仕事だったんですが、その一方で、毎日真っ黒な画面ばかり見ているのはどうなんだ、と思うようになりまして。いつしか、ブラウザの外に出たい、ディスプレイだけの世界から抜け出したい、という気持ちでいっぱいに(笑)。それで、小さな頃からの夢だった、ロボットづくりをしようと、ユカイ工学を設立したわけです。2007年でした」
ーー当時はWeb2.0の全盛期。Webの世界ではいろいろなサービスがスタートした時期でした。
「そうですね。MySQLとかApacheといった無料のツールが充実した時期でしたね。その一方で、アメリカで雑誌『Make』がスタートしたり、Arduinoが登場したりと、ハードウェアの世界でも何かが起きそうな空気が漂いはじめた時代でもありました。それまで数十万円、数百万円もしたようなセンサーが一気に安くなったり、もうちょっと経った頃にKinectなんかも出てきたんじゃなかったかな(編集部注:Kinectの登場は2010年)」

ーー当初からロボットをつくろうと考えていたんですか?
「家庭用のロボットをつくること、それと、その定義みたいなものを作りたいと思っていました。たとえばパソコンやスマホにはそれぞれ、誰もがイメージする形や機能がありますが、それを家庭用のロボットでつくりたい、と。ただ、2007年当時と今とでは、そのあり方は大きく変わってきていますね。ネットワークのスピードが圧倒的に速くなったことに加えて、我々の生活の身近なところにセンサーが付く、そんな環境が現実的になってきたというのがその大きな理由です。これは、会社を立ち上げた当時にいろいろとお世話になった大阪大学の石黒浩教授もおっしゃっていることなんですが、以前はロボットをつくるとなると、本体にいろいろな機能を詰め込んで、知能を持たせることを考えていた、と。それが今は、本体をできるだけシンプルにして周囲にあるセンサーやネットワーク、そしてクラウドといった“環境”を活用していくという方向に変わってきた」
インターフェイスとしてのロボット
ーーユカイ工学がリリースした「BOCCO」は、まさにシンプルなロボットですよね。
「そうですね。BOCCOは歩いたりしないし、我々の身の回りのことを何でもしてくれるようなロボットではありません。そういう意味ではシンプルなロボットですね。現段階でできることといえば、ドアに付けたセンサーと連動して、たとえば子どもが家に帰ってきたことを知らせてくれること。それに BOCCOに話しかけたメッセージをスマホに送ってくれる、といったことです。将来的には、音声認識のような機能を追加していけたらと考えています」
ーーどういうきっかけでBOCCOをつくったのですか?
「最初のヒントは、我が家の子どもなんです。うちは夫婦で共働きなもので、子どもが学校から帰ってきても家に誰もいない。親としては心配なので、様子を確認したいのですが、そのために小さな子どもにスマホを持たせるのには、ちょっと抵抗があったんです。そんなことを考えているうちに『今の世の中には、家族内のコミュニケーションを補助してくれるツールがない』ということに気が付きました。スマホを持っている者同士であれば、FacebookとかLINEとか、いくらでも方法があるのに、家族のコミュニケーションのためのツールがない。その結果、遠くにいる友人がどこでラーメンを食べたのかはよく知っているのに、子どもがお昼に何を食べたかはまったく知らないなんてことが起きてしまう。それはちょっとおかしいなと。スマホは便利な機器だと思うんですが、子どもやお年寄りのように、それを使えない、使いたくない人もいるんですよね。アプリを入れるなんて面倒くさいって感じている人もたくさんいます」
ーーそこでBOCCOのようなロボットが役に立つ、と。
「そうですね。いろいろな機能の窓口になれればいいのではないかと。IoTがすごいって言われても、それをイメージできないユーザーはたくさんいます。そういう人たちにも、とっつきやすくなるんじゃないかと思うんです。」
ーーなるほど。ただ、そのための機器がBOCCOのような、かわいい形をしている必要はあるんでしょうか? たとえば海外で話題の「Nest」のような形状でもいいのでは?
「ユーザーにちゃんと使ってもらえるもの、つまり、生活の中に入り込んでいくものをつくりたいと考えた時に、日本ではこういうデザインがいいのではないかなと考えました。家庭で、特にリビングで使う場合、そこに置いてもいいかどうかを判断するのは女性や子どもであるケースが多いでしょうから、やっぱりかわいいものの方が受け入れられやすいだろうな、と。ちなみに、僕としては、ロボットはリアルな人間型よりも『となりのトトロ』のような、よくわからない不思議な生き物のような形の方が楽しくていいと思っています。僕らの話すことがちょっとわかる、なんか不思議な形をしたロボットが、リビングにちょこんと居る。そういう感じがいいんじゃないかなあ」
文化や生活、日常の感覚からの発想
ーー 「日本では」という一言がありましたが、かわいいものを受け入れるのは、日本独特の事情でしょうか?
「海外の人に比べて、BOCCOに話しかけることに抵抗を感じない人が多いと思います。むしろNestのような、いかにも端末、といったものに話しかけることに抵抗を感じるのではないでしょうか。それって日本人の生活とか、文化みたいなところに由来するものなんじゃないかなと思うんです。日本には、たとえば『こけし』みたいなものを、なにげなく部屋に飾っておくみたいな文化があるじゃないですか」
ーーありますねえ。私の実家のテレビ台にも、なぜかこけしが飾られています(笑)。生活に密着するIoTでサービスや製品をつくっていくには、日常の感覚から発想しないといけない、ということですね。
「アメリカで『GoPro』が生まれて、他のメーカーが似たような製品を出しても、変わらずに支持を得ているのは、やっぱりアメリカには、ひたすらサーフィンをやったり、山で自転車に乗ったりしている人たちがたくさんいるっていうのが大きいと思うんです。当然、つくり手の中にもいるんでしょうし。そういう日常から発想しているから強い商品になっているんだろうな、と。そうそう、日本には『スーパーマリオブラザーズ』のように、キャラクターを使って、世界に広がる強力なプラットフォームをつくり上げた歴史もありますよね。そういうところもよく見ておくといいと思っています」
ーーなるほど。では今後、ユカイ工学ではどんなロボットをつくろうと考えていますか?
「そうですね。やっぱり生活の中に入っていくロボットとして、“日本の家族の形が以前はどういうもので、今、どうなろうとしているのか”とか、“かつては近所の人が助け合ったりしてなんとか解決していた問題を、今後どうすべきか”みたいなところに注目しています。生活の中の、ちょっと足りない部分を解決していく。スマホじゃできないアレとか、アレとか‥‥」
ーーそこは企業秘密ということですね(笑)。青木さんのロボットのお話は、IoTのサービスやハードウェアに取り組む上での大事なポイントになると感じました。どうもありがとうございました。
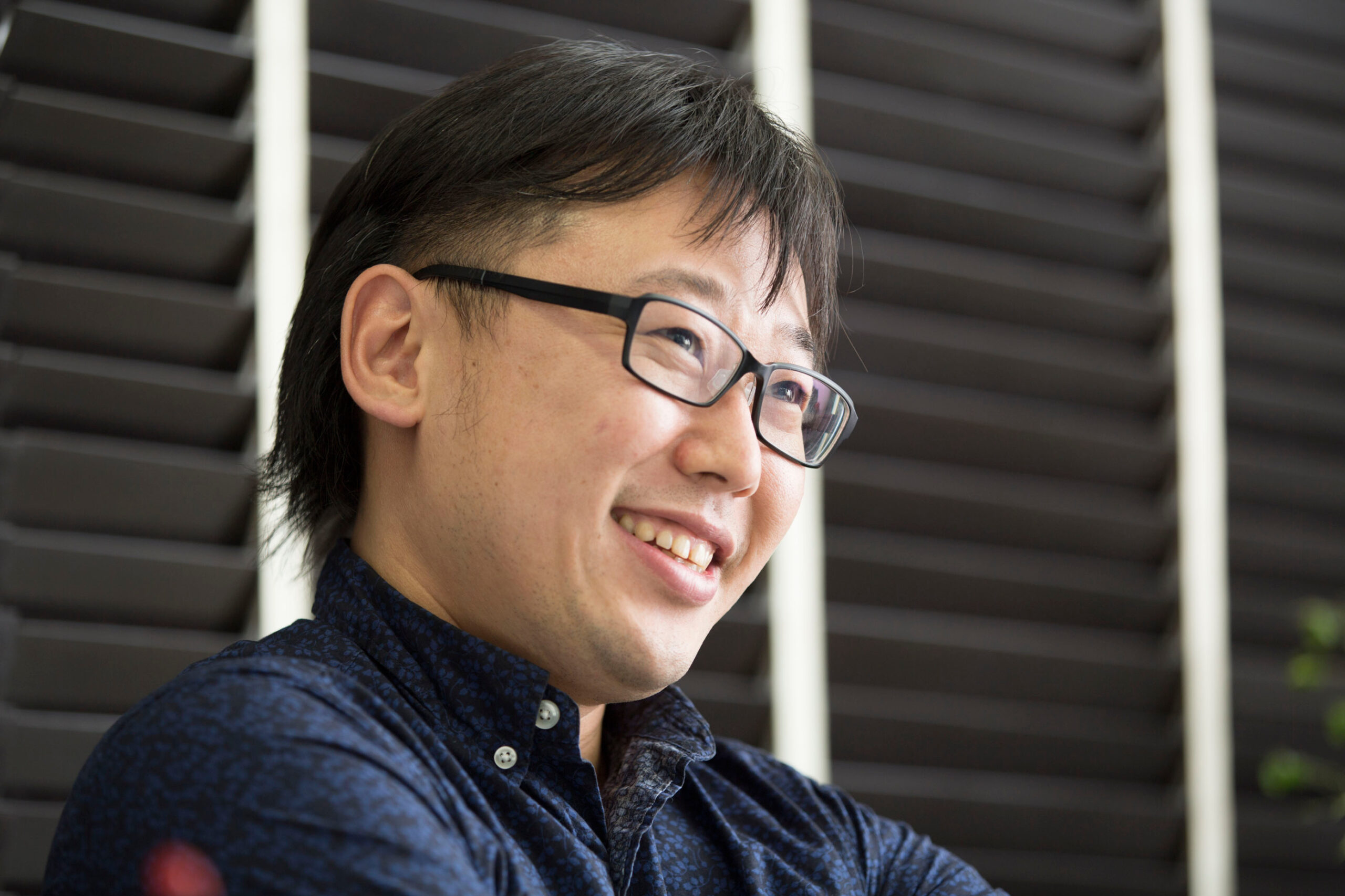
- 青木俊介
- (株)ユカイ工学 CEO 2001年東京大学在学中に、チームラボ(株)、CTOに就任。その後、ピクシブ(株)のCTOを務めたのち、ロボティクスベンチャー「ユカイ工学」を設立。ソーシャルロボット「ココナッチ」、脳波で動く猫耳「Necomimi」、フィジカルコンピューティングキット「konashi」など、IoTデバイスの製品化を多く手がける。2015年7月、家族をつなぐコミュニケーションロボット「BOCCO」を発売し、2015年度グッドデザイン賞を受賞した。
