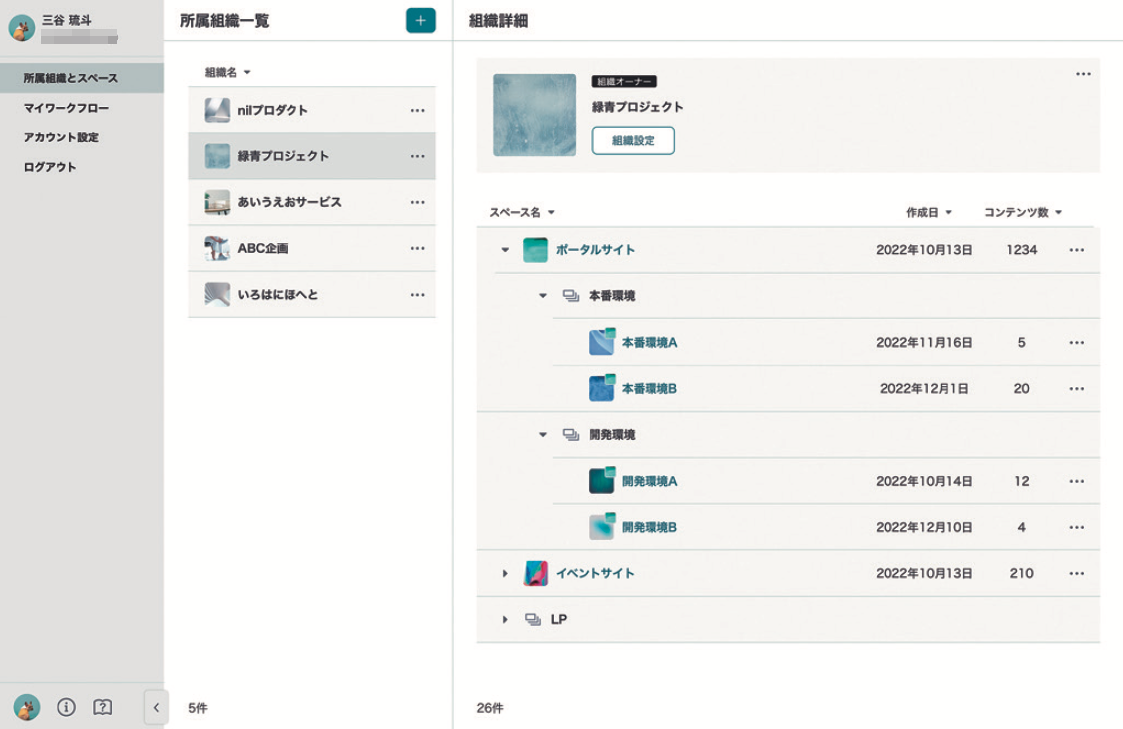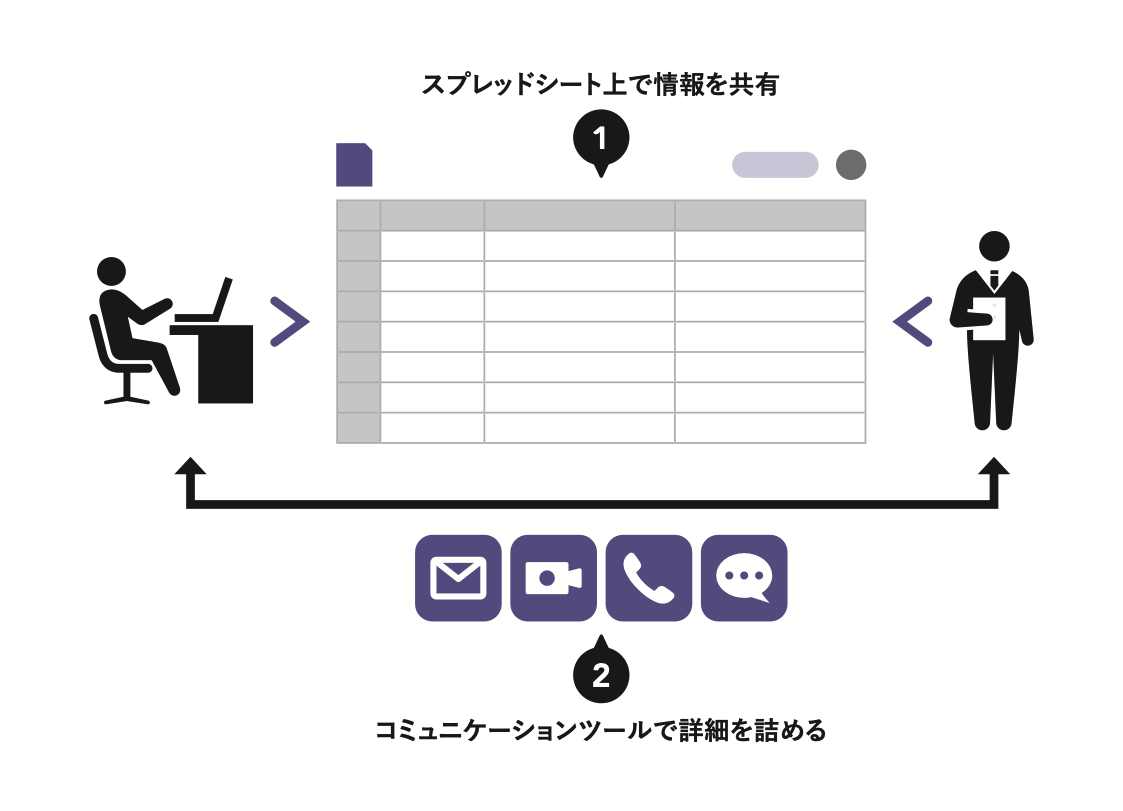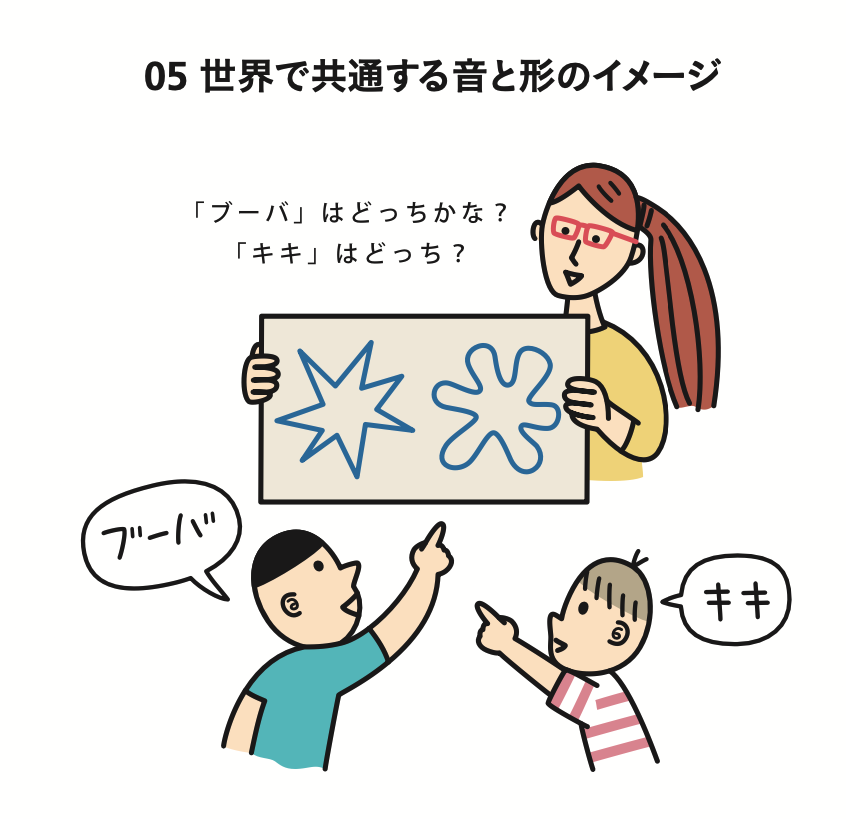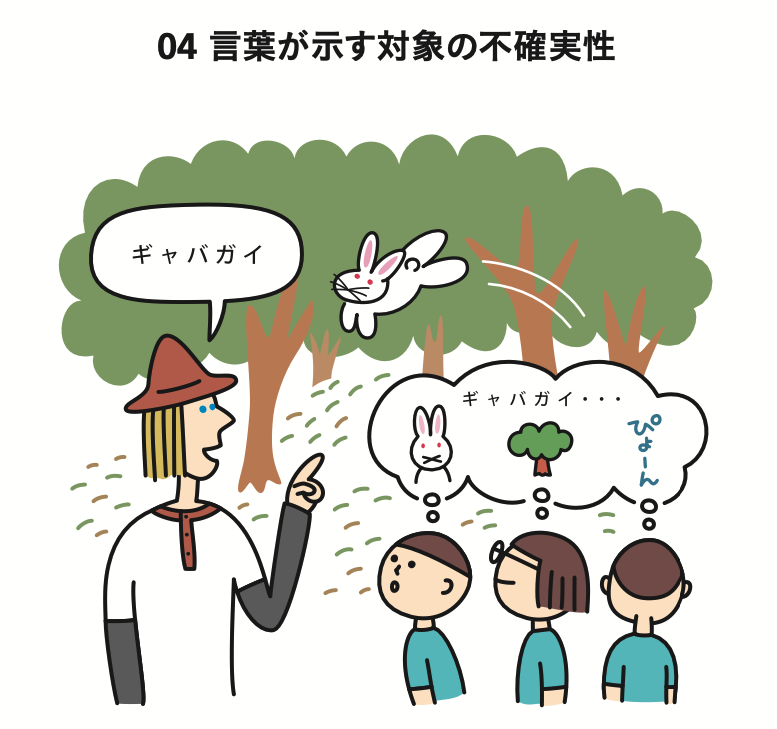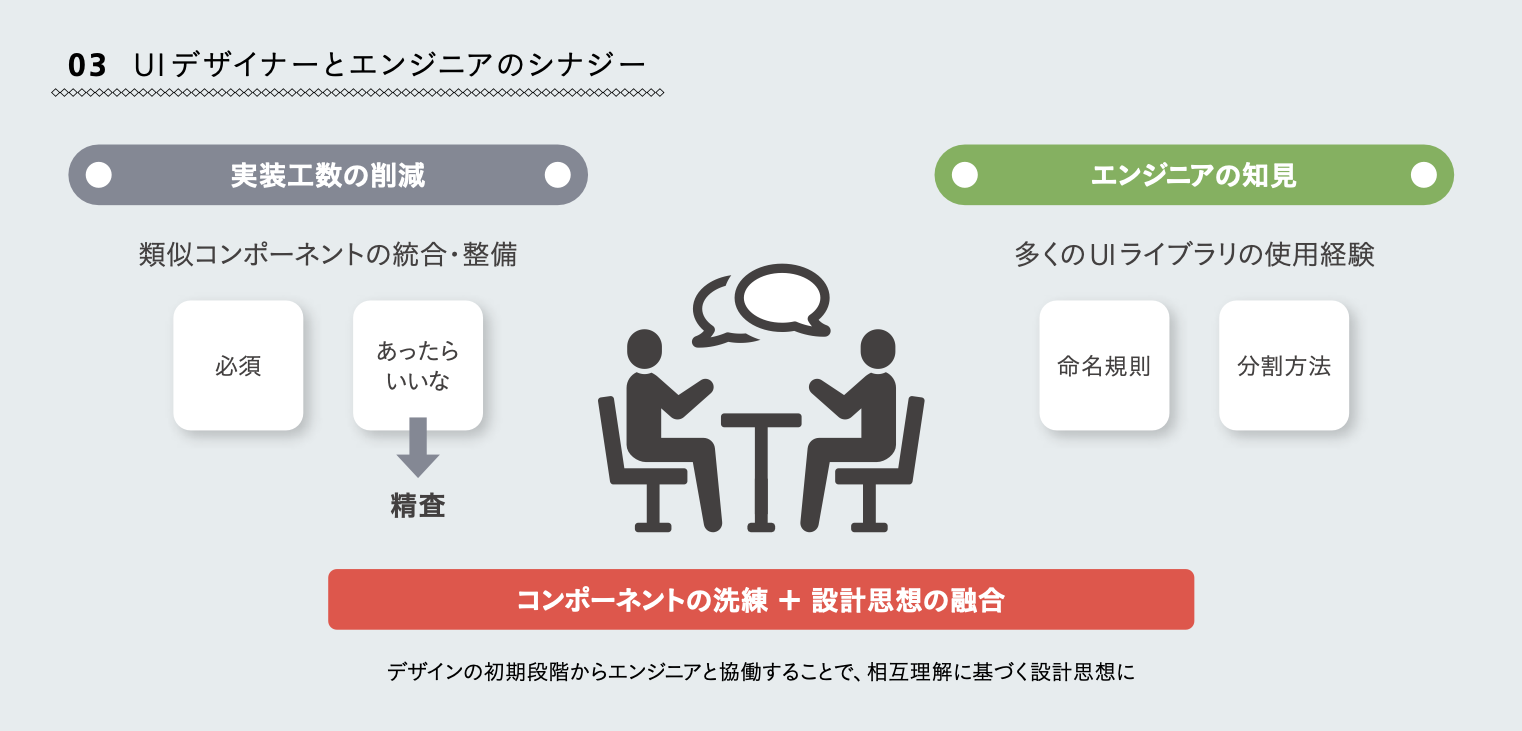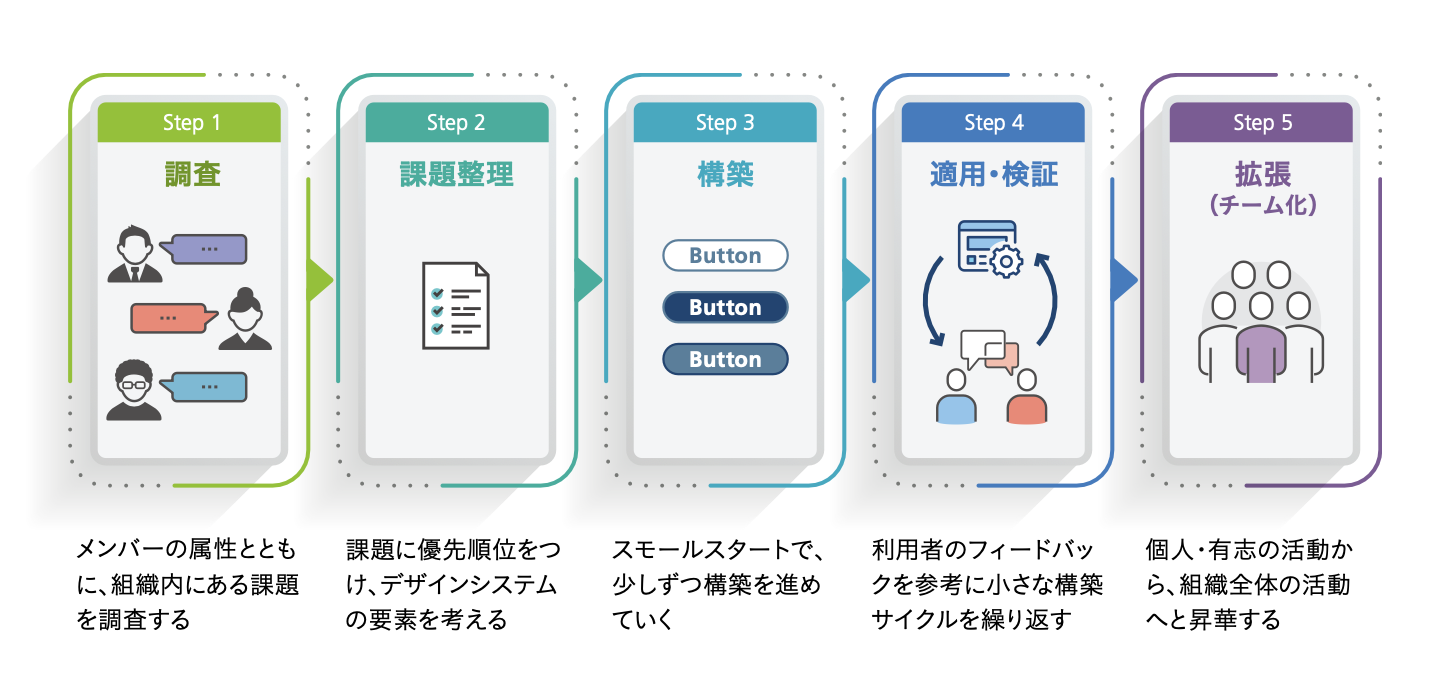オウンドメディアの大変なところと、でもやっぱりやってよかったこと。
それぞれに事情も狙いも異なるオウンドメディア
「木村石鹸 よもやま噺」の峰松加奈さんと「KURANDマガジン」の辻本翔さん。二人のオウンドメディア担当者が訪れたのは、本誌連載でおなじみの未来食堂。ランチタイムのピークを過ぎるまで、まずは二人の話から聞いてみることにする。
─ 峰松さんは、以前から「KURANDマガジン」に注目していたとか。
峰松 読んでいて面白くて、しかも日に何本も記事をアップしているすごいメディアだからです。しかも、どうやら酒屋さんが運営しているようだとわかって、俄然興味が湧いたんです。
辻本 はい、うちはもともとECの酒屋をやっていまして、その宣伝のためにオウンドメディアを始めました。おかげさまで、いまは店舗も手がけるようになり、日本酒中心の「KURAND」、梅酒の「SHUGAR」、焼酎の「HAVESPI」と、それぞれお酒の販売・店舗とメディアを結びつけて運営をしています。さらにはお酒全般の情報を発信する「NOMOOO」というオウンドメディアも手がけています。
峰松 それだけの媒体をどんな体制で動かしているんですか?
辻本 社内は僕一人なんです。もちろん原稿を書くところまではやりきれませんので、執筆は依頼をしています。
峰松 すごいな…。私が担当しているブログなんて、週に1本で精一杯なのに。
─ 木村石鹸のオウンドメディアもスタッフは峰松さん一人なんですよね。そもそもどんな経緯で始めたんですか?
峰松 私は1年ほど前に木村石鹸に転職してきまして、広報とか商品企画とか、いろいろな仕事の一環としてオウンドメディアを担当するようになったんです。
辻本 うちの運営会社(リカー・イノベーション)は起業してわずか3年なんですが、木村石鹸さんには歴史がありますよね。
峰松 家庭用洗剤や工業向け洗浄剤をつくって93年になります。ただ歴史がある反面、ネットを使ったマーケティングとは無縁な会社でした。それが若い副社長の旗振りで、その体制を改めよう、と。でも「お金かける意味があるの?」みたいな声もあって、実現するのは大変だったんです。そのあたりの経緯についてはまとめた記事がありますので、「オウンドメディアをやりたいけど」、と悩んでいる方にぜひ読んでいただきたいです。
─ さすが広報さん、宣伝がうまい!(笑)
一同 (笑)
目標設定から記事のネタ集めの仕方まで
起業時からメディア戦略を重視したKURANDマガジンと、社内の新しい武器としてオウンドメディアを始めた木村石鹸。対照的な二社である。
─ それぞれ、メディアの目標、KPIをどう設定したんでしょうか。
辻本 メディア開設当初は、お酒に特化した内容で大量に記事をアップし、バズらせて話題を呼ぶことをメインに考えていました。たくさんの人にサイトに来てもらうことで、ECサイトでの販売につなげていこう、と。その目標は、グノシーなどキュレーションサイトに記事を取りあげていただいたこともあって、なんとか達成することができました。いまはそれに加え、開業した飲食店の予約につなげることを重要なKPIと考えています。
峰松 辻本さんのお話と比べてしまうと、小さなことなんですけど、「とにかく更新を続けること」を目標にしました。週に1本でもいいから諦めずにやっていこう、と。いま振り返ると、それが良かったと思います。当時の社内の意識のあり方を考えると、そこで閲覧数や売り上げを目標に掲げて結果を求められていたら、身動きが取れなくなってしまったと思います。
小林 それで1年続けてきて、売り上げは変わったんですか?
峰松 直接オウンドメディアと結びつけていいのかはわからないんですが、楽天での売り上げは3倍になりました。
小林・辻本 すっ、すごい!
峰松 ただ、元がそれほど大きくないので…。売り上げへの貢献というと、お客様や取引先から「ブログで木村石鹸のことを知りました」「いつも更新を楽しみにしている」と言ってもらえたことの方が、大きなことかもしれません。
─ 小林さんは、ブログ「未来食堂日記」を書かれていますが、特に「事業計画所」はすごく話題になりましたね。
小林 そうですね。メディアにも取材をしてもらいましたし、大きな効果があったと思います。でも、当初は屋号で呼んでもらえず「事業計画書が話題の食堂」とか、私の経歴から「元エンジニアが始めた食堂」といった切り口の取り上げられ方ばかりでした。そういう意味では、なんとかみなさんに屋号で呼んでもらう、名前を覚えてもらう、というのが当初の目標でしたね。
峰松 事業計画書、うちの副社長も読んで泣いたって言ってました(笑)。
小林 本当に?(笑)。嬉しいな。でもね、実を言うとPV程度しか見てないので、アクセスの詳細がよくわからないんです。PVが一番いい記事は、キャベツの千切りのコンテンツ。包丁などの道具の選び方と使い方を紹介しているんですが、本当に使っているプロが勧めている、というのが人気の理由なんでしょうね。
辻本 KURANDでもいろんな記事があるんですが、各店舗の店長が書くブログは人気ですね。文章がうまいというわけでもないんですが。
小林 記事を書いている当人に「確信があるかどうか」というのはとても大事なことだと思うんです。未来食堂日記でも、「こうしている」というテーマの記事は、全般的に評判がいいように思います。もちろん私の場合、作り手イコール書き手だから、特に、そういう傾向が強いのかもしれませんが。
─ 峰松さんの記事にも「試してみた」系は多いですよね。
峰松 「掃除してみた」「使ってみた」といったノウハウものはやっぱり評判がいいです。同じような内容の記事は、大手の家庭用品会社のサイトに体系的にまとまっているのですが、ものによっては、こちらの手作り記事の方が人気が高かったりするんです。それも多分、実際に試した上での「確信」があるからなんでしょうね。実際に私、やってますし(笑)。
辻本 同感です。「中の人」の情報には価値がある。ただ、蔵元さんの記事については工夫が必要だと思っていて…。
読みたくなる記事はどう書けばいいのか
辻本さんからの問題提起は、記事のつくり方を考えさせるものだった。それぞれのメディアにあった「いい記事」とは?
─ 辻本さんからあったのは、「中の人」の記事にも、考えないといけないポイントがあるというお話でしたね。
辻本 例えば酒造りをする蔵元さんのお話には面白いものが多いのに、本人たちはそうは思っていない、ということ。なかなか取材をさせてくれないんです。
峰松 それ、私も同感です。洗剤の開発段階で行われている実験なんて、外から来た(転職してきた)人間にとっては全部面白く見えるんですけど、昔からそこにいる現場の社員にはそうは見えないんだと思います。「こんなの面白いの?」って。普通のことすぎて、魅力があるなんて思いもしないんでしょうね。
辻本 もう一つは、「蔵元の歴史」みたいな記事って、マニアックな内容なので、ライトな層に届くような、「バズる記事」にはならないんですね。
─ その場合どうするんですか?
辻本 たとえばそこにいる「面白い人」に焦点を当てたり、「普通の日本酒とここが違う!」みたいな角度を付けた内容にするといった工夫をします。ただそれって、なかなか難しいんですよね。

峰松 私も工場の話、研究開発の話を取りあげていますが、バズよりも、読んでくださったその方が、木村石鹸の商品を応援しようという気持ちになれるかどうかを大事にしています。とはいえ、たくさん読まれると嬉しいんですけど(笑)

─ 峰松さんは記事づくりにおいて基準にしているようなことはありますか?
峰松 基本的には、私自身が「面白がれるか」、「感動できるか」といった感覚を大事にしています。
その点で言うと、現在75歳になる社長に、木村石鹸の歴史を聞いたロングインタビュー記事は、読んでくださった方にとても評判が良かったんです。それこそ「大阪の商売人の一代記」みたいな感じで山あり谷あり、ジンとくるような話まであって。昔ながらの社員も知らない話がたくさん出てきて、会社にとってもいい財産になったな、と。
─ 峰松さんのおすすめ記事を伺いましたので、辻本さんにも印象深い記事を伺いたいと思います。
辻本 これまで記事にいろいろな角度をつけて、多くの方に読んでもらう工夫をしてきたんですが、これまで一番読まれているのは、やはりというべきか、日本酒の基礎を解説したページなんです。ベーシックなんですが、これだけ読めば日本酒の選び方が変わる、といった内容で、今もアクセスは伸び続けています。
やっぱり、こういった強い記事を出していかないと、と時々思い返すんです。
小林 唐突で申し訳ないんですけど、さっき峰松さんから頂いた木村石鹸のカタログ、石鹸の匂いがするのね。素敵!
辻本 あ、ほんとですね!
峰松 多分、商品と一緒にカバンに入れていたからだと思います。でも言われてみるとこれ、いいですね。これから得意先に伺う際には、香り付けしてから持って行こう(笑)。自分たちでは気づかない魅力って、このことですね。
小林 このカタログもオウンドメディアですもんね。そう考えてみるとオウンドメディアは「らしい」ってことが大事ね。
最近、私はブログではもう言いたいことを言い切れない感じがあって、本くらい書かないと伝わりきらない、って思ってるんです(P144参照)。でも、いろんな形があっていいですよね。もちろんブログはブログで続けていくと思いますけど。

─ 小林さんにまとめていただいたところで、おひらきにしたいと思います。オウンドメディアで悩む担当者の方は、この座談会のように、他の会社の人と話してみると、ヒントが見つかるかもしれませんね。皆さん、ありがとうございました!