16年ぶりの日本語版登場に刮目せよ! 『ABOUT FACE インタラクションデザインの本質』監訳者まえがきを先行公開!
8月19日、奇しくも『Web Designing』10月号と同日にマイナビ出版から発売される『ABOUT FACE インタラクションデザインの本質』(Alan Cooper、Robert Reimann、David Cronin、Christopher Noessel ・著)。2008年に発売された第3版日本語版は長らく品切れで、ネット書店で非常な高値で中古品が販売される状況となっていた。それから16年、ついに第4版の完全日本語訳が発売となる。上野学・監訳、ソシオメディア株式会社・訳という最強の布陣でお送りする本書の、「監訳者まえがき」を特別に先行公開。監訳者である上野さんの熱いメッセージと本書についての思いの詰まったまえがきを、ぜひ読んでいただきたい。

執筆者プロフィール
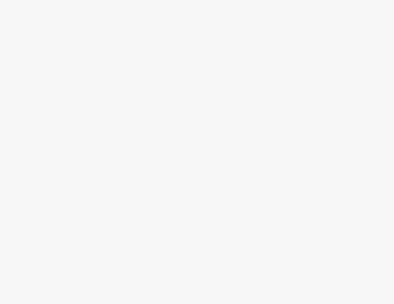
上野 学さん
デザインコンサルタント/デザイナー。各種ソフトウェアのヒューマンインターフェース設計およびユーザビリティ評価に従事。ソシオメディアにおいてデザインメソッド開発を担う。執筆、講演など多数。
監訳者まえがき
端的に言ってこの『About Face』は、デジタルプロダクトのデザイナーたちにとって、「できれば読んだ方がいい」ものではなく、「これを読んでいない者はデザインの仕事をしてはいけない」といえるほど重要なものである。
これを読まずにデザインすれば、ほぼ間違いなく、本書で繰り返し指摘されるような愚劣なものを作ってしまうことになる。なぜなら著者も言うとおり、インタラクションデザインは専門的なスキルであり、一般的に考えられている方針の多くが実は間違っているからだ。もしあなたが未読のデザイナーで、自分はそれなりにうまくやっていると思っているなら、これを読んで愕然とするに違いない。自分は何もわかっていなかったと気づき、いてもたってもいられなくなる。かつての私がそうであったように。
本書は2014年に出版された『About Face: The Essentials of Interaction Design』第4版の全訳である。日本では、第3版の邦訳『About Face 3 インタラクションデザインの極意』(アスキー・メディアワークス、2008年)から16年ぶりの登場となる。この重要書籍の日本語版が長らく手に入りにくかったことは、日本のデジタルデザイン業界、特に新しくこの分野に足を踏み入れた若いデザイナーたちにとって大きな痛手だったと思う。デザイン教育者たちは最高の教科書がオンラインの中古市場で異常な高騰を見せていることに頭を悩ませていた。本書の刊行は、そのため非常に意義深いものになるだろう。
原著『About Face』の初版がアメリカで出版されたのは1995年で、日本でも同年に邦訳版が『ユーザーインターフェイスデザイン: Windows95時代のソフトウェアデザインを考える』(翔泳社)として出版された。邦訳のタイトルにもあるとおり、当時は Windows 95 の発売で空前のパソコンブームとなっており、ワールドワイドウェブの普及もあって、デザイナーたちがデジタルの分野に興味を持ちはじめた時代だった。ただし彼らの意識はグラフィックデザインやメディアアートの延長にあったため、道具としてのソフトウェアのデザイン、つまりユーザーインターフェースデザインについて学ぼうとする者はあまり多くなかった。
当時、専門家による、GUI の利点や評価方法についての研究にはすでに一定の蓄積があった。しかしそれらは基本的に、工学的もしくは認知心理学的な観点からの分析的な取り組みであり、人が使うものとしての GUI をデザインするという、統合的な活動を体系化するものではなかった。その理由は、コンピューター科学やシステム開発などの領域でユーザーインターフェースがそれほど重視されていなかったということもあるが、それ以前に、そもそも、GUI がもたらす現象的な対象世界が、かつての建築に匹敵するような根源性をもって、ソフトウェアデザインという創造的カテゴリーを生み出していることに、人々がまだ気づいていなかったからなのである。
『About Face』以前、ユーザーインターフェースに関心を持つデザイナーたちが思想的な拠り所にしていたのは、Apple がデベロッパー向けに発行していた「Human Interface Guidelines」だった。現在も公開されている同ガイドラインの初期版にあたる1986年版には、冒頭に「Philosophy」という章があり、そこには、コンピューターはユーザーの人間性をベースにデザインされるべきであるということが説かれていた。ユーザビリティや人間中心デザインといった言葉はまだ広まっていなかったが、その考えにデザイナーたちは大いに感化された。私もそのひとりだった。それで私はユーザーインターフェースのデザインを専門的に行う仕事に就いたのだった。しかし、人間性をベースにデザインするということの実践的な意味を本当に理解したのは、『About Face』を読んだ時である。私は雷に打たれたような衝撃を受けた。
たとえばそれまで私は、入力の不備をエラーメッセージで指摘してくれるのはコンピューターならではの親切な仕組みだと思っていた。アプリケーションを閉じる時に「保存しますか?」とダイアログで問いかけてくるのは GUI らしいフレンドリーな振る舞いだと思っていた。しかしそれは完全な間違いだった。なぜそれが間違いなのかは本書を読んでいただくとして、とにかく『About Face』によって私の視点は180度転換した。まさに「about-face(回れ右、考え方を完全に転換すること)」したのである。
筆頭著者のアラン・クーパーが本書の中で求めているのは、徹底的な人道的デザインの追求だ。それはユーザーの人間性を尊重することであり、システム提供者の高慢さに対抗することである。クーパーは、技術モデルをベースにしたデザインからユーザーモデルへの移行を訴える。本書ではテクノロジードリブンなデザインに対する批判が繰り返されるが、そこに説得力があるのは、クーパー本人が筋金入りのプログラマーだからである。彼はプログラマーが実装モデルに従って製品をデザインしてしまう心理を十分すぎるほど理解していた。だからこそ、ユーザー視点の欠如はプログラマーの怠慢であると言い切ることができた。そしてそんなデザインが許せなかったのである。クーパーは2007年のインタビューで次のように言っている。
“多くのプログラマーは、技術的な部分に焦点を当てています。彼らは、技術的な課題を解決することや、タスクや機能を実装することが自分の役割だと考えます。そういったことを行わなければならないのは確かですが、それらはあくまで人間であるユーザーが成し遂げようとしていることの傘の下で行わなければなりません。”(*)
パーソナルコンピューターやスマートフォンが普及し、人々が日常的にソフトウェアを利用する機会が増えた。同時に、それらを開発するソフトウェア産業も拡大し、より多くのプログラマーやデザイナーがそこに携わるようになった。そしてユーザーエクスペリエンスという概念に注目が集まり、事業者たちはユーザーを「もてなす」ための方法を次々と考えはじめた。しかしそれらの多くは、実際には、ユーザーに事業者にとって都合のよい行動をとらせるためのビジネス施策であり、プログラマーやデザイナーは、そのためのタスクや機能を作ってユーザーを誘導することが自分たちの役割だと認識するようになった。
クーパーが指摘するさまざまな問題は、制作側の態度に関係している。彼らに欠けているのは、ユーザーのことを、消費者や顧客や作業担当者である前に、自分と同じ人間として捉える態度である。インタラクションデザインはシステムの振る舞いを作ることだが、単純に、それは制作者や制作を指示する者の態度を反映したものになる。不遜な態度は、ダークパターンと呼ばれるような自覚的な策略というより、非対称性の無自覚的な肯定としてデザインの全レイヤーに結合する。多くのアプリケーションはユーザーに正しい操作をすることを強要している。そこで問われるべきはなのは、「アプリケーションの基準では理解できない情報をユーザーが入力した場合、それは誰の責任になるのだろうか?」というクーパーの素朴な投げかけなのである。
本書のイントロダクションにもあるとおり、1995年の初版以降『About Face』は改訂を重ね、急速に発達するデジタルデザイン分野の要求に応えるように内容を拡充させてきた。第2版(2003年)ではアラン・クーパーの名前を一躍有名にした「ペルソナ」手法についての解説が追加され、第3版(2007年)ではデザインプロセスに関する記述が大幅に増加した。そして本書の底本となる第4版(2014年)では、各種デザインリサーチの手法やデザイン組織のあり方を含めるなど「ゴールダイレクテッド」なデザインを実現するためのプロセスがさらに体系化され、本文中に登場するサンプルにはウェブアプリケーションやモバイルアプリケーションに関するものが大量に採用された。またソーシャルメディアの倫理的側面など、現代的な広義のデザイン課題にまつわる言及も追加された。その結果『About Face』は、デジタルプロダクトをデザインする上で知っておくべき事柄を完全に網羅したバイブルに成長した。
ただし、改版の過程で何度も構成が組み直されているので、セクションごとに書かれた時期が異なり、同じ話が繰り返されていたり、その内容が少しずつ違った表現または主張になっているところがある。また全体の基調には当初のスコープが残っており、この日本語版の出版が原著(第4版)から10年経っていることもあって、内容に古さを感じさせる部分があるのは否めない。たとえば現在(2024年)、ユーザーインターフェースデザインを伴うシステム開発のほとんどはウェブアプリケーションもしくはモバイルアプリケーションになっていると思われるが、本書で詳説しているテクノロジーの多くはデスクトップネイティブのアプリケーションに関するものであり、ファイルシステムについての指摘なども、クラウドベースの環境が普通になった現在ではあまり当てはまらないものも多い。さらに、OSベンダーやアプリケーションベンダーがこの約30年の間に『About Face』から示唆を受けた結果(だと思う)、現行バージョンではすでに問題が解消しているようなところも多くある。
しかし一方で、本書が指南するコアなメッセージは、今もまったく色褪せていないばかりか、人々が仕事や生活の中で接するソフトウェアが爆発的に増えたことで、問題の深刻さはむしろ大きくなっていると言える。我々を取り巻く状況を見渡せば、テクノロジーが変わっても、同じような稚拙なメンタリティーが再生産され続けているのがわかる。それらの誤謬を鋭く転回する本書は、その意味で今も新しい。
本書には、コンバージョンを高めるための表現や、事業をグロースさせるテクニックなどについては書かれていない。ユーザーにとって意味のある道具としてのソフトウェアを作る、というテーマに集中している。デザインはビジネスのサブセットではない。デザイナーは自律的な倫理感を持ってテクノロジーを解放する。そのために必要なのは、ソフトウェアプロジェクトにおけるデザイナーの主体性である。本書には GUI の実装技術的な解説が多く含まれるが、ソースコードや特定のフレームワークの解説は出てこない。そのかわり、ユーザーにとっての具体的な現象と、ソフトウェアとしての抽象的な記号を結びつける、独特な観点が提出されている。実際には既成のコンポーネントやライブラリーに任せてしまうような部分も、改めてすべて抽象化して説明している。そこでデザイナーは、ソフトウェアデザインの統合的パースペクティブを訓練されることになる。この本がデザイナーにとっての強力なエンカレッジになると私が思うのは、そのような点である。
本書でクーパーは、自らが遭遇した失敗エピソードの数々を大袈裟な文句とともに開陳する。被害妄想ではないかとつい笑ってしまうが、そのコミカルな自虐的表現の中に彼は、天才的なコメディアンたちがそうするように、権威的なものに絡め取られた現状への大きな警鐘を込めているのである。それに気づけば、笑いは涙に変わるだろう。クーパーはソフトウェアに人間のように振る舞うことを求めているが、それは擬人化を意味しない。むしろ彼は善人の顔をしてユーザーの行動に割り込んでくるシステムを強く批判する。彼が言っているのは、ソフトウェアは社会性とリスペクトを持って、ユーザーを人間として扱わなければならないということである。そのメッセージを受け取れば、少し古く見えるような図版が示す「バカげた」デザインも、味わい深い寓話として永続化され、本書をまさにバイブルとして立ち上がらせる。私は、はじめて読む読者、特に若いデザイナーたちが、一刻も早く『About Face』の強烈な洗礼を受けることを願ってやまない。
*)UX Pioneers:アラン・クーパー氏インタビュー
Visual Basic開発の裏話、About Face執筆の経緯、ペルソナ手法がどのように考案されたかなど、充実した内容のインタビュー記事
※ 監訳者まえがきは原文ママ
