Facebookのコンテンツ
こんにちは。“あなたの「ふつう」をあつらえる”未来食堂のせかいです。
今回のお題は「Facebookのコンテンツ」。
未来食堂は定食屋なので定食コンテンツは持ち合わせているのですが(ご飯の炊き方や麦茶の出し方とか)、Facebook(以下、Fb)のコンテンツに関してはちょっとピンぼけです。というのも、Fbだけでなくすべての“伝える”という行為で私が意識しているのは、「伝えるということは“あなた”に宛てた手紙だ」という、ただその一点だけなのです(詳しくは、2016年8月号に書いたところです)。
今回はコンテンツそのものではなく、コンテンツをつくる人に視点を向けてみます。
「これは絶対受ける!」と思っても反響がイマイチだったり、常にコンテンツをつくり続けないといけないプレッシャーだったり(Fbのような投稿型SNSだとより顕著でしょう)。質の良いコンテンツをつくり続けるのは大変なことです。
そういったつくり手の苦悩を和らげる“サポーター”という立場に、最近よく目がいきます。というのも先日、未来食堂の本を書き下ろしで2冊上梓したのですが、その過程で“編集者”というサポーターに幾度も助けられ、その振る舞いを目の当たりにしたからです。
サポーター(編集者)は、自分で作品をつくるわけではないけれど、作品のあるべき形をイメージし、時に方向を指示します。自分は一文字も手を加えられないのに、その作品に責任を持つ。そういった立ち位置が興味深いのです。
本を出すためには何万字かの執筆があり、ある程度の期間取り組まないといけません。そういう意味でFbコンテンツづくりと同じです。走り続けるその過程で、コンテンツをどうつくるか。作者側の視点だけでなく、つくる人と併走する編集者的視点から眺めてみても、新しい発見がありそうです。
つくり手を励まし、褒めて伸ばす。行く末(出来上がりの作品)がわからなくてもじっと待つ。今はSNS黎明期であり、まだまだ「つくり手」「つくるもの」自体に意識が向きがちですが、これからはこういった「支え手」の存在も意識されていくことでしょう。
先日、キングジムさんとの座談会にお邪魔しました。特に印象的だったのは、Fb担当のお二人が何度も「コメントをもらえたらほんとに嬉しい」と仰っていたこと。つくったコンテンツに対してリアクションをもらう嬉しさは、どんな立場であれ変わらないのだなと感じました。
良いサポーターとは何か、難しく考える必要はありません。あなたの会社のFB担当に「あの投稿、おもしろいね」と少し声をかけるだけでいいのです。それが、どれだけその人の力になることか。定食コンテンツを毎日つくっている私が、太鼓判を押しますよ。
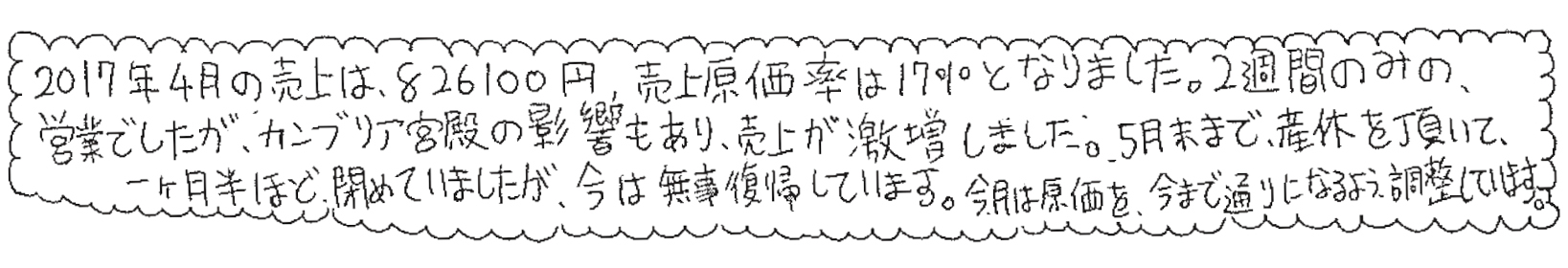
※この連載のネタ帳はGitHub Gistにて公開しています。
http://miraishokudo.com/neta/web_designing
内容についてご質問、アイデアのある方はお気軽に。

- Text:小林せかい
- 東京工業大学理学部数学科卒業後、日本IBM、クックパッドで6年半エンジニアとして勤めた後、1年4カ月の修行期間を経て「未来食堂」を開業。自称リケジョ。その他、詳しいプロフィールは公開されている情報をご覧ください。 https://goo.gl/XpwnMQ

