《対談:原研哉×小玉千陽》“言語化ブーム”における違和感の正体「デザイナーとして重要なのは、頭の中のキラキラを外に出したとき、どう色褪せないようにするか」

制作の現場では、提案の場で、あるいは成果物に対して、デザインを言葉で説明することを求められる機会が増えています。デザインの文脈から見た「言語化」とは、さらに「言葉」とはどのようなものなのか。著書等で繰り返しデザインを論じてきた原研哉さんに、言語化を探求しながら現状に疑問も持つ小玉千陽さんが聞きます。(前後編の前編)
デザインを語ることは
もうひとつのデザイン
小玉千陽(以下、小玉) 私は大学在学中からデザイナーを目指してキャリアを積み、この業界で仕事をするようになりました。理系出身という背景もあって、最初の数年はロジックで語れることが自分の強みだと考え、そこに凝り固まっていたなと今になって思います。
でも最近、スキルとしての言語や効率化など表層ばかりが叫ばれているように感じて、本来もっと柔らかい抽象的な部分を言語化することを目指していくべきではないか、と気になっていました。
原研哉(以下、原) なるほど。僕は割とテキストを書くほうですが、必ずしも論理でデザインはしていなくて、感覚的な捉え方が先行しています。直感的にある答えができてしまった。それを後から説明するために言葉を使っているような気がします。
具体的にデザインをして、形になったものに対して語る必要が出てきたときに、言葉にする。これは、もう一つのデザインの行為であると思っているところがあります。
小玉 デザインすることと、言葉で書くことは別のレイヤーで考えているということですか?
原 そうです。ただ、現実的にはデザイナーは“説得業”ですから、自分が気付いた面白さや素敵さについては、言葉を重ねて相手にわかってもらうしかありません。デザインの説明やプレゼンのためにコンセプチュアルな説明を書くことは、最近確かに多いかもしれません。
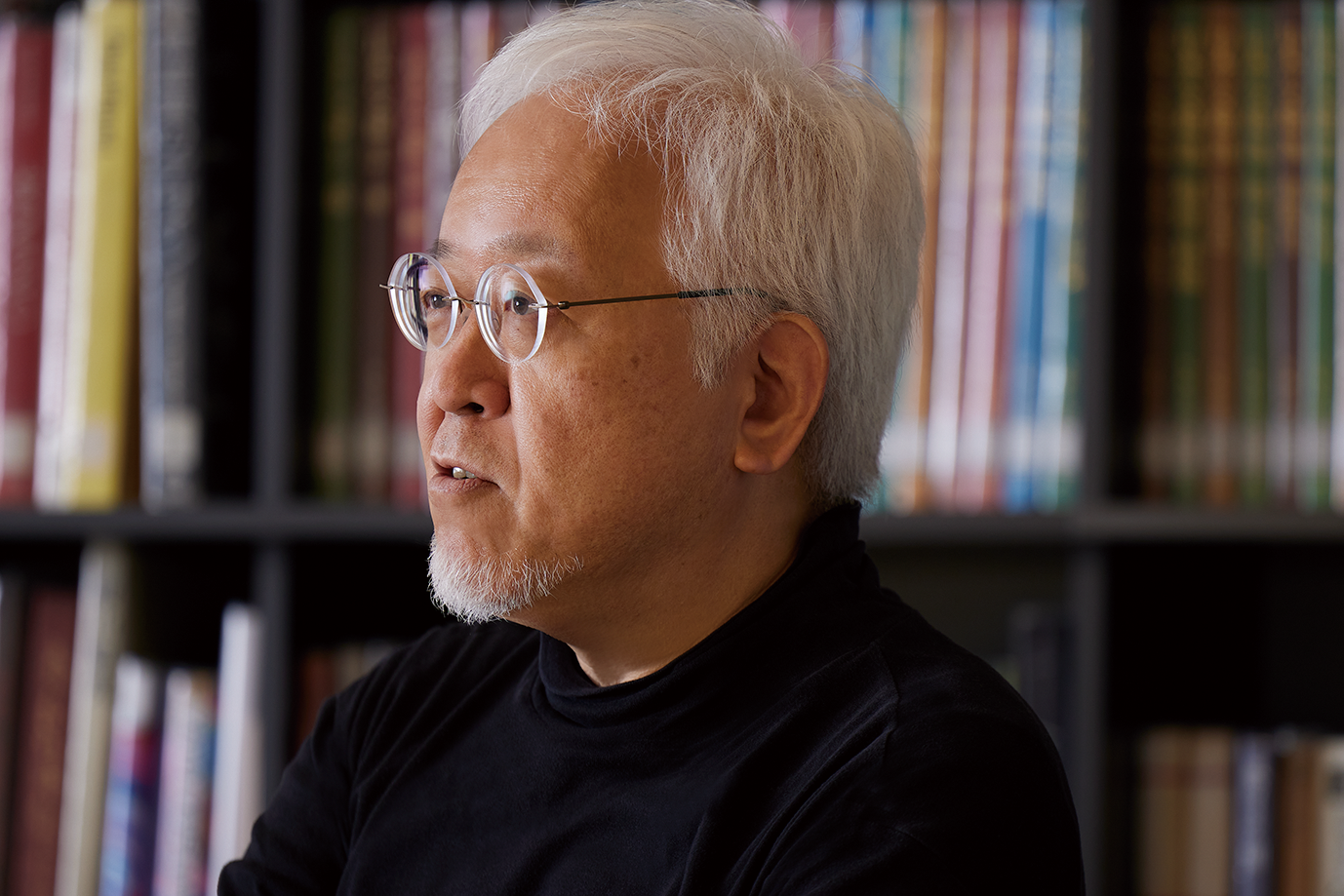
小玉 現在のような世の中において、デザインはもっとポジティブで人を惹きつける本質的な強さがあるはずと思いつつ、実際に現場の意思決定はどうしてもロジックに寄りがちだったり、守りに入りやすかったりするので、それを私の言葉で変えられないだろうかと日々思っています。
原 精緻で強靭なロジックというより、人が普通は感じていないところにスッと綺麗にメスを入れないと伝わらないことがあるし、デザイナーという仕事を積み重ねてきているから見えるものもあると思います。
デザイナーに限った話でなく、いい仕事をしている数学者や科学者、音楽家はとてもいい言葉を持っています。スペシャリストというのは、比喩的に言うとそれぞれその分野の“木”に登っているわけです。数学者は数学の木に登り、デザイナーはデザインの木に登る。そしてある高みを超えると同じ光景が見え始める。同じものをそれぞれ別の木から見ている感じでしょうか。
こうした人たちがいい言葉を持っているのは、そこからしか見えない風景を的確に語っているからだと思うのです。独自のポジションから風景を見ることが重要であり、最初から言葉を獲得しようとすると違うトレーニングになってしまう気もします。
小玉 確かに。それは言語化ブームのようなものに私が感じていた違和感の原因かもしれません。
原 数学者の岡潔さんは、「数学は情緒だ」と言っています。同じく数学者の藤原正彦さんは『祖国とは国語』(新潮文庫)を著して、数学を勉強するよりまず国語を勉強するべきだと言うのです。それも非常に腑に落ちる。数学者は数式で語るばかりでなく、真理のようなものに近づくほど饒舌になるようにも見えます。思考がこぼれ落ちないように、いい言葉、いいリズムで表現したいと思うようになるのかもしれません。
小玉 本質に近付けば近付くほど、原理原則も分野を超えてつながるのですね。
原 見えているものをただ描写すればいいのであって、感情の高まりまで伝える必要はないわけです。俳句のように、見えているものを忠実に写生するための言葉の使い方を、そういう人たちは身につけている気がします。
小玉 せっかく日本語を母語とするなら、俳句や古文の表現にもっと興味を持ってもいいと思います。世界を見れば英語や中国語が大事と言われますが、日本ならではの言葉を拠り所にしてもいいのではないでしょうか。

原 そうですね。国際的であることは、多言語を話すこととは違うと思います。1つの言語であっても、語るべき内容と高度な表現を持てば、それは自然と国境を超えていくものです。
小玉 言語を、国境を越えるためでなく、物事や事象を深く理解するためのものと捉えるのですね。
原 何かいいものを捉えることができれば、国の壁は自然と超えていくのではないでしょうか。デザイナーとして鍛錬してきた世界をどうやって自然に言語化していくか、自分の中に耳を澄ませていくことが重要ではないかと思います。
頭の中のイメージから
言葉がほとばしり出る
小玉 原さんは、普段の体験やインプットは画として頭に残りますか? 言葉として残りますか?
原 言葉としては残っていなくて、漠然としたイメージ、情景のようなものがあるかもしれません。言葉は、出してみて初めて「こんなものが出た」と感じることが多いです。
呆れられるかもしれませんが、時々自分の書いたテキストを読んで「どうしてこんなことが書けたのだろう」と自分で不思議に思うことがあるんですよ(笑)。頭の中に言葉があってそれが吐き出されたのではなくて、何かのイメージが弾みとなって、言葉がほとばしり出たというか。少し無責任なようですが、そういう感じです。
小玉 お仕事では、スタッフの皆さんにどのようにフィードバックをされるのでしょうか?
原 僕はたくさんスケッチを描きます。言葉も使いますけど、頭の中に湧き出るのはやっぱりイメージです。キラキラした素敵なことを考えている。デザイナーとして重要なのは、その頭の中のキラキラを外に出したときにどう色褪せないようにするか、ということでしょう。
おそらく、誰でもアイデアは素敵なのです。だけどプロフェッショナルは、素敵なアイデアを素敵なまま外に出せる技術を持った人たちなのですね。それは言葉で出す人もいるし、スケッチで出す人もいる。僕はどちらかというと言葉は後で、スケッチの方が先に出る。だから、いつもスケッチを描いて見せながら対話をしています。
小玉 私はつい言葉で伝えすぎて、スタッフを萎縮させてしまうことがありました。デザイナーなら、スケッチで伝えることがやっぱり大事なのかもしれません。
原 スケッチには頭の中のキラキラを外に出そうとした、その初体験が描かれているわけですよね。このアイデアのポイントは何なのか、そのキワをとにかく逃さないよう懸命に描こうとしている。
アイデアをスケッチにしている感じと、伝えたいことを言葉にしている感じは、そんなに違わないと思います。輝きをどう損なわずに表現できるか。だから、やっぱり重要なのは「感じる」ということでしょうか。
(後編へ続く)

Text: 笠井美史乃 Photo: 石塚定人
※本記事は「Web Designing 2024年6月号」に掲載した記事を一部抜粋・再編集したうえで掲載しています。
